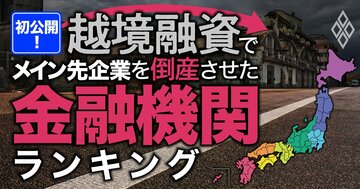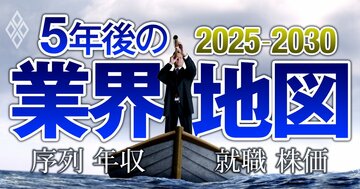1930 to 1939
資本主義の限界を補う「統制経済」の時代
1930年代は、日中戦争の勃発から戦時体制の確立に至るまで、日本が「総力戦体制」へと舵を切った時代でした。国家総動員法の下で統制が一気に強まり、軍需優先での生産体制が整備されていきます。
1930年代の前半は大蔵大臣の高橋是清による積極財政政策(高橋財政)で高成長が実現し、供給能力が高まり、需給バランスが保たれるようになった時代でした。1936年には「自動車製造事業法」が制定されましたが、これは軍備拡張を視野に入れ、自動車産業を戦略的に育成しようとした国家主導の政策です。法律の制定によって、新たに自動車を製造するには政府の許可が必要となり、さらに国産部品の使用が強く求められるようになります。ここで、国産メーカーであるトヨタ(当時の豊田自動織機製作所 自動車部)や日産自動車は、「自動車製造指定会社」として政府からの正式な許可を得て、本格的な製造体制を整えることができました。これが、のちの日本の自動車産業の飛躍につながる転機となりました。
企業の大規模化、重化学工業化が進むにつれ、綿紡績業では五大紡(鐘紡、東洋紡、大日本紡、日清紡、富士瓦斯糸紡)に集約されたほか、製紙、鉱業、セメント業、人造肥料、毛織物業、製糖業、電力業でも水平的合同が進行しました。銀行部門では、金融恐慌後の1927年に成立した銀行法により銀行合同が進行、大銀行への預金集中が起こり、三井・三菱・住友・安田・第一・三和の六大銀行体制が成立しました。このようにビッグビジネスが生まれ、企業集中が起きたのもこの時代の特徴です。
そんな好景況の中、日本は1937年の日中戦争を境に統制経済へと移行していきます。
1930年代後半になると、日本は戦時体制の構築とともに、国家がモノ・カネ・ヒトの流れに深く介入するようになりました。その背景には、1929年の世界恐慌で、当時の資本主義市場経済が行き詰まっているという認識もありました。加えて、ソビエトでの社会主義革命の影響も無視できなかったと思います。
1936年末以降、軍需増大を見越した輸入の急拡大、それによる国際収支の悪化、日銀券の膨張により需給バランスが崩れ、物価が高騰し始めました。政府は1937年1月から輸入許可制に踏み切り、経済統制が始まったのです。
同年、国家総力戦体制を構築するため、経済・産業・資源の統制を計画・立案・調整する「企画院」という官庁が設立されたのですが、統制経済は単なる軍事目的のための非常手段という意味合いではなく、資本主義経済の限界を補う「もう一つの経済モデル」として受け止められていた側面もあったのではないかと思います。
戦争の拡大に伴い、企業への統制はどのように強まったのでしょうか。
企業に対する世論の圧力が強まっていきました。三井銀行によるドル買い事件(1931年)が「国益に反する」と非難され、1932年には三井財閥の團琢磨が暗殺される「血盟団事件」も起こりました。こうした企業・財閥批判の高まりを受け、企業側も社会的責任を自覚し始めます。三井銀行が「三井報恩会」という社会・文化への助成を目的とする団体を設立したほか、松下幸之助も1932年に「水道哲学」を発表しました。「産業人の使命も、水道の水の如く、物資を無尽蔵にたらしめ、無代に等しい価格で提供する事にある」と提唱したのですが、こうした発言も当時の企業批判の高まりが背景にあったのではと思います。
統制は特に「モノ」の面で急速に強まり、重化学工業への投資が急激に進みます。そのための資材を輸入に頼るので、外貨が不足してきます。軍需資材は国の存亡に関わるため最優先とされ、相対的に重要度の低い民需品の輸入は、大幅に減らされました。その結果、市民が必要とする物資が不足し、モノの価格が上がり、配給制度や価格統制、さらには労働・消費の統制も導入されるという、まさに統制が統制を呼ぶ構造になっていきました。
「カネ」の面でも、統制が強化されました。政府は軍事費をまかなうために日本銀行に赤字国債を引き受けさせ、通貨供給量を急増させました。結果としてインフレーションが進行し、政府は国民に対して貯蓄を奨励する「貯蓄増強運動」を展開するとともに、金融機関に対して不要不急の産業への貸出抑制、軍需産業への融資促進などの金融統制を実施しました。