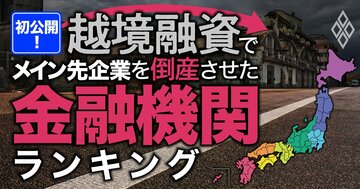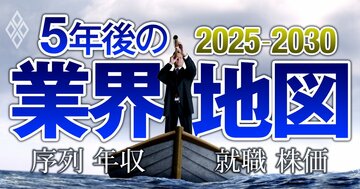1960 to 1969
構造変化と成長の歪みが生まれた時代
1950年代後半からの高度経済成長が実現し、60年代は日本が経済大国へと上り詰めていき、経済と社会の構造に大きな変化が生じ、一方で公害など社会問題が起こり、経済成長の負の部分が露見するようになりました。
ちょうど明治維新から100年目に当たる1968年に日本の国民総生産(GNP)が西側諸国で第2位になったことが、高度経済成長の帰結として日本が経済大国へと変貌した象徴的な出来事といえるでしょう。
この時代には、主に3つの面で社会構造が大きく様変わりしていきます。
1つ目は、就業構造の変化です。1955年には全就業者の41%が第1次産業に従事していましたが、1970年には14%にまで減少。代わって第3次産業従事者は36%から52%へと大幅に増加し、企業に雇用される人の割合は65%に達しました。生活の場が都市中心に移り、働き方も変わっていく中で、日本社会全体の構造が変容していったことがわかります。
2つ目は、産業構造の変化です。1955年の第1次産業、第2次産業、第3次産業の割合はそれぞれ23%、29%、48%でしたが、1970年にはそれぞれ9%、36%、58%となり、第1次産業の比率が急激に下がり、第2次、第3次産業の割合が増加していきます。
特に、製造業の重化学工業化がいっそう進み、戦前の産業は繊維・食料品・窯業・木材中心だったのが、戦後は金属、化学、機械にシフトしていきました。
3つ目は、地域構造の変化です。1955年の都市部と農村部の人口比率は56対44でしたが、1970年には72対28と、都市への人口集中が顕著になっています。特に若年層が三大都市圏に集中して移動し、新しい流行や消費のスタイルを生み出す原動力となりました。都市に定着した若者たちは核家族を形成し、一家に一つ必要とされるような家電製品の需要を大きく押し上げました。当時は、どの家庭も同じようにテレビを買い、冷蔵庫を買い、洗濯機を買っていくという、横並びの消費が一般的でした。いまのように、ユニクロを着ながらベンツに乗るというような多様なスタイルは、まだ生まれていなかったと思います。
日本が経済大国となった結果、国際関係にも大きな変化が生じたのでしょうか。
1960年代中頃からは資源輸入のための外貨獲得、為替固定制(360円)の維持などにより、国際収支は黒字基調へと転じます。また、近代工業部門への革新的投資が続けられた結果、日本の輸出競争力はいっそう強化されました。
経済協力開発機構(OECD)への加盟など国際的な地位が向上する一方、外国からの日本に対する圧力が強まっていったのです。農産物の輸入増加、非関税障壁の撤廃、アメリカのドル防衛に対する協力、円切り上げなどが要求されるようになりました。日本は貿易自由化を進めていましたが1960年代半ば以降、輸入制限品目を減少させ、本格的開放体制への移行を進めました。
資本取引についても、1967年7月から3回にわたって自由化を実施し、外資に対して段階的に道を開いていったのです。資本自由化は当初「第二の黒船襲来」とまで騒がれ、外資による日本企業の乗っ取りが懸念されましたが、それは杞憂に終わり、むしろ日本企業の海外投資が活発化する結果となったのです。
1960年代は東京オリンピックや新幹線開通など、経済成長を象徴するようなイベントが相次ぎました。
それらのイベントは、国民に経済成長の成果を実感させ、その関心とエネルギーが爆発させるものだったといえるでしょう。東京オリンピックは、戦前の1940年に東京で開催することになっていた第12回オリンピック大会が、日中戦争の激化により中止となって以来、国民の悲願となっていました。東京オリンピック開催に合わせて開通することとなった東海道新幹線も、戦前から高度成長期にかけて達成された日本の技術水準の高さを象徴するものでした。新幹線は近代日本が生み出した技術開発物の最高傑作と評価され、日本の産業技術の優秀さを世界にデモンストレートすることになったのです。
また、1970年に大阪で開催された日本万国博覧会も、1940年にオリンピックと同時開催される予定であったが、やはり中止となった「紀元2600年記念日本万国博覧会」のリベンジ開催でした。6400万人の入場者を集めたこの大阪万博は、博覧会史上でも空前の規模のものであり、日本の高度経済成長の成果を世界に誇示するものでした。しかし結果としては高度成長時代に幕を引くイベントともなったといえます。
この時代は公害など、成長の「歪み」も顕在化していきます。
市民の間で福祉や環境といった生活の質への関心が高まり、社会的な要請も多様化していきました。1967年の経済社会発展計画では「均衡の取れた充実した経済社会」が目標に掲げられ、1969年度の『経済白書』では「豊かさへの挑戦」という副題の下、成長の成果を社会的不均衡の是正に振り向ける必要性が説かれました。
1970年には環境庁が設置され、公害・環境問題への対応が国の政策課題として本格化。さらに、全国の大学では学園紛争が吹き荒れ、新しい形の市民運動も盛り上がりを見せました。工業立地や電源開発への社会的制約も強まり、企業活動は単なる成長から、社会的責任や環境との調和を求められる時代へと移行していったのです。
戦前戦後という大きな時代の転換を経験した昭和のこの50年間から、学べることは何でしょうか。
この頃の日本企業は、経営者は現場を知る従業員出身者が多く、自然と「従業員を大切にする」意識が備わっていたと思います。しかし現在の経営者は、社内よりも資本市場や株主に向きがちなようです。その結果、賃上げよりも内部留保や配当、自社株買いといった施策が優先されるケースもあります。個人的には、自社株買いにはあまり本質的な意味がなく、収益力の向上こそが本来の経営課題だと感じています。
また、日本企業には歴史的に「キャッチアップ局面で力を発揮する」という特性があるように思います。第1次世界大戦を契機に進んだ外国企業との提携や技術導入、高度経済成長期の「追い付き追い越せ」の努力が典型です。ただし、ある程度まで到達すると安心してしまい、その勢いを持続できない傾向がある。
現在の日本経済も、再びキャッチアップすべき時期にあるのに、「日本は特別」といった内向きで自己肯定的な空気がむしろ勢いを削いでいるように感じます。
若者もかつてに比べ、海外留学や異文化への接触が減っている。ITやAIではアメリカや中国に大きく差をつけられているにもかかわらず、「最初から勝てない」と諦める空気もある。それでは新たな成長の芽は育ちません。本来、日本の家電メーカーが切り開くべきだったスマートフォン市場を逃したのも、「もうトップになった」という思い込みが成長を止めてしまった一因かもしれません。
いまの日本は、もはやトップランナーではないという自覚を持ち、もう一度「追い付く」意識を取り戻すべきだと思います。ただし、自前主義に固執する必要はありません。アメリカのIT企業が海外の技術者を多く採用しているように、海外の技術や人材を積極的に受け入れ、学びながらみずからを高めていく、かつてのような柔軟さが求められています。外の力を借りつつ、みずからの強みを育てていく姿勢が、これからの日本には不可欠だと考えています。
◉聞き手|久世和彦 ◉構成・まとめ|錦光山雅子、久世和彦
◉リード文|宮田和美