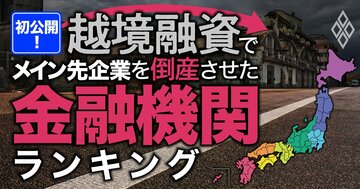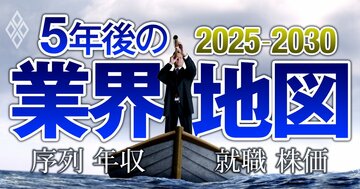1940 to 1949
終戦の破綻と戦後経済基盤形成の時代
1940年代は日中戦争勃発から新体制運動の下、戦時経済統制へと移行し、軍需優先で生産力の拡充が図られ、国家総動員法の施行で統制がいちだんと強まりました。国民徴用令や賃金統制令などで軍事産業体制が整備されたうえで、太平洋戦争の勃発に至りましたが、戦局が悪化する中、資源不足、労働力の制約による生産性の低下、食糧事情の悪化により戦争遂行能力を失い、敗戦へとつながりました。終戦直後の財閥解体、労働改革、農地改革といった経済民主化政策から戦後復興が始まります。
国内の「モノ」「カネ」両面での統制が進むに従い、「ソト」、つまり国際経済でも統制が強化されました。輸入品の選別と数量制限、貿易管理、外国為替の統制などが次第に厳しくなり、経済の外部依存度が意図的に減らされていきます。その一方で、国内の物資不足と輸送力の限界により、1940年にはすでに民需は1937年の水準を下回り、戦況の悪化に伴って1944年秋以降には軍需生産すら低下に転じました。こうして統制経済は、民需生産の急減、悪性インフレの深刻化という形で国民の生活水準を大きく切り下げ、最終的には戦争とともに破綻しました。
敗戦で日本は産業のインフラをすべて失ってしまったのでしょうか。
戦時統制経済で得られたものがすべて敗戦とともに消え去ったわけではありません。むしろ、戦後の復興と高度成長を支えた構造のいくつかは、戦時下で育まれたものでした。たとえば、重化学工業は爆撃による損傷はあったものの基幹設備が比較的多く残され、復興の出発点となりました。また、軍需生産体制の中で整備された下請け制度は、戦後のサプライチェーンの原型となり、現在の系列構造につながっていきます。金融でも、軍需企業への資金供給で、特定の金融機関を指定して資金を流す「軍需会社指定金融機関制度」が整備されたことで、企業と銀行の結び付きが強まりました。これが戦後のメインバンク制や企業グループ形成の土台となり、日本型金融システムの一部として定着していきます。
企業経営でも、戦時中に進んだ「所有と経営の分離」が、戦後の企業ガバナンスの前提となりました。戦時下では企業経営者になるには政府の認可が必要であり、能力のある経営者が求められました。また、財閥も自己資金では重工業投資をまかない切れず、次第に株式公開を進めるようになりました。これにより、オーナーの株式所有率が下がり、戦後の財閥解体の下地が形成されていきました。
結果的に、大株主資本主義から、銀行、一般株主、専門経営者がバランスを取る戦後型の企業支配構造への移行が始まっていたのです。
このように、戦時統制経済は一面では国家による強権的な介入であり、国民生活を厳しく制限する体制でしたが、同時に戦後経済の基盤となるさまざまな制度が形づくられた時期でもあったのです。
終戦を経て、日本の経済構造はどのように転換していったのでしょう。
敗戦後の日本において、連合国軍司令部(GHQ)による占領政策の経済産業面での目的は、大きく2つに集約されます。一つは日本の物理的な戦争遂行能力を排除すること、もう一つは侵略性を生む構造的な要因を取り除くことでした。前者では、軍需工業の解体が進められました。賠償として日本国内の工場設備や工作機械の「現物」が被害国に引き渡される一方で、重工業の再建や設備投資に対しても厳しい制限が課されました。
次に、後者の構造的な要因の除去として、財閥解体・農地改革・労働改革の「三大改革」が実施されました。財閥の本社が解体され、その株式は一般に売却されます。加えて、経営層の公職追放によって企業トップが若返り、大株主や先輩上司からのしがらみを免れた経営ができる環境が整うことになりました。農地改革では、小作農への土地移転が進み、労働面では労働組合法の制定などにより、労働者の地位が向上します。これらの改革は、結果として所得水準の引き上げと都市の消費市場の拡大をもたらしました。
こうした経済構造の刷新と並行して、日本の復興政策の中核となったのが「傾斜生産方式」です。鉄鋼と石炭という基幹産業に資源と資金を重点的に投入することで、生産の基礎を整え、そこから他産業へ波及させる狙いがありました。この方式は一定の成果を上げましたが、戦後の物資不足によりインフレが深刻化します。そこで、GHQは米デトロイト銀行頭取だったジョゼフ・ドッジを派遣、復興政策の改革に着手させました。ドッジは、日本経済を「竹馬経済」だと表現しました。政府の補助金とアメリカの支援という2本の支えがあり、これに依存した状態では自立とはいえないと指摘したのです。
この考えに基づき、「経済安定九原則」が策定され、総予算の均衡、財政支出の抑制、補助金の削減、復興金融金庫の債券発行停止などが実施されました。
また、為替レートを1ドル=360円に固定し、市場経済への移行を促しました。これによりインフレは沈静化しましたが、企業経営の不振、失業の増加が深刻化し、また、国際競争に直接さらされることになった企業は合理化の推進によるコスト削減に努めなければならなくなりました。