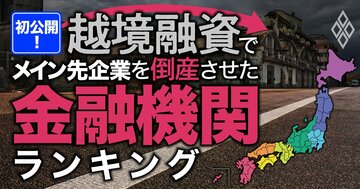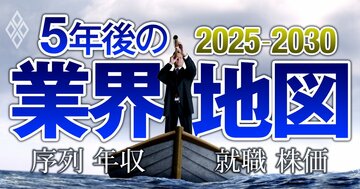1950 to 1959
高度経済成長へ離陸の時代
1950年代には戦後インフレがドッジラインの実施で収束し、朝鮮戦争による特需で消費需要が大幅に増大する消費景気が到来し、空前の高度経済成長が訪れ、日本は経済大国へと急速に変貌を遂げることになります。
不況感を一掃したのが、1950年に勃発した朝鮮戦争です。日本は兵站基地として機能し、米国軍からの特需が発生しました。
「糸へんブーム」「金へんブーム」と呼ばれる紡績業や金属産業が活況を呈し、1951年には工業生産と実質GDPが戦前水準にまで回復しました。ドッジラインが実施されていた間に企業の供給能力が上がったため、インフレを起こすことなく特需を享受できたのです。
この間、企業は資本の蓄積を進め、輸出志向型の経営戦略を展開していきます。内部留保の重視が成長戦略の中心に据えられ、経営者には長期的視野が求められるようになりました。同時に会計制度も整備され、財務の透明性が高まります。こうした中で、経団連などの経済団体が形成され、政策提言を通じて経済運営にも関与していくようにもなりました。占領終了後は、独占禁止法の緩和などを背景に、企業集団の再形成が進みます。銀行が中心となり、系列融資によって企業集団が形成されたほか、株式の相互持ち合いや系列商社の活用を通じて、かつての財閥のような企業の結び付きが復活しました。ただし、近年ではその結束力は弱まりつつあります。
戦後復興が達成された後の、日本経済の課題は何だったのでしょうか。
特需に依存した経済からの脱却です。そのために輸出振興策と相まった産業政策が展開されます。当時の産業政策は、3つの柱がありました。
1つ目は、外為法・外資法による外貨と外資の統制です。限られた外貨を、製造機械や原材料など、国益にかなう輸入に集中させ、外資企業による投資に厳しい条件を設ける一方、日本の産業発展に役立つ技術提携には門戸を開きました。
2つ目は、企業の資本蓄積を促すための税制上の特別措置の導入です。たとえば、減価償却制度で「特別償却」が認められ、企業が設備投資にかかる費用を早期に経費計上できるようにしました。実質的に税負担が軽減され、企業は利益を再投資しやすくなり、生産性の向上や技術革新の後押しとなりました。
3つ目は、産業金融システムの整備です。日本輸出銀行、日本開発銀行、中小企業金融公庫といった政府系金融機関の設立、国家資金を運用する財政投融資計画の確立、投資信託、貸付信託の開始と長期信用銀行法の制定により、企業は中長期的な投資や大規模な施設のための資金を安定的に調達できるようになり、その後の高度成長期へと歩み始めました。
1950年代後半からの高度経済成長が実現した要因は何ですか。
主に民間固定資本の形成(投資)が、経済成長を牽引しました。高度経済成長の要因としては、輸出主導説と投資主導説がありますが、後者のほうが正鵠を得ているといえるでしょう。
自動車産業での設備投資が鉄鋼業や工作機械、部品工業での設備投資を促す、「投資が投資を呼ぶ」サイクルが形成されていきました。また、設備投資や技術革新は労働生産性を高め、賃金・所得を上昇させ、消費市場の拡大につながりました。さらに、欧米などの先進国から導入された革新技術は新製品をもたらしたり、品質を向上させたり、製品のコストダウンを実現し、市場を拡大させました。このように、設備投資が経済の好循環をもたらす要因となったのです。加えて、戦後の日本では軍事支出が抑えられたため、投資は民生需要中心の固定資本に集中されました。このことも経済成長に大きく寄与したのです。
ただし、輸出の役割も無視できません。高度成長期には経済成長率と輸出とが負の相関関係にあったことが知られています。
つまり、不況の時は輸出が伸び、好況の時は輸出が減るのです。これは、輸出が内需変動の影響を調整する役割を果たしていたことを示唆しています。また、資源の乏しい日本にとっては、資源輸入の原資を稼ぐために輸出の伸長が必要だったのです。
高度経済成長を支えたもう一つの要因として、消費の拡大が挙げられます。
経済全体を支えていたのは投資だけでなく、個人消費も大きな柱でした。消費支出の拡大が企業にとっての市場拡大の兆しとなり、それがさらなる投資や技術開発の動機付けにもなったのです。結果として、電気製品など耐久消費財の品質が高まり、価格も抑えられ、多くの家庭に普及し、大衆消費社会の幕開けとなりました。
戦後の日本人にとってアメリカの生活様式は憧れの的でした。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、トースター、自動車、高速道路といったものが理想として受け入れられ、アメリカに追い付き追い越せという意識が社会全体に広がっていきました。
これを可能にしたのが、賃金と所得の向上です。春闘による賃上げ、所得税減税などを通じて、給与所得者の実質所得が毎年のように上昇し、貯蓄率も高まりました。若年層の所得上昇に加え、中小企業と大企業の格差縮小や、農村部での土地所有の平等化といった社会的変化も背景となり、人々は次第にみずからを「中流」と感じるようになります。この「中流意識」が生活の安定感を支え、内需の拡大へとつながっていきました。
私自身、高度成長期の時期は中学入学から大学卒業後の数年間に当たり、まさに高度成長とともに生きてきたという実感があります。今年は電気炊飯器、来年は冷蔵庫、その次は洗濯機、さらに掃除機と、家庭の電化が急速に進み、生活の質が目に見えて向上していく様子を、日々の暮らしの中で体験しました。