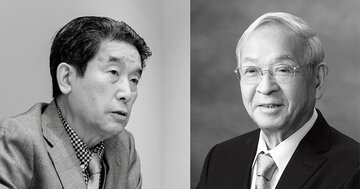1980 to 1989
我が世の春と慢心の時代
1970年代は挫折や問題噴出の時代でありながら、調整という観点では日本が誇るべき成果を上げました。危機への対応力を示し、低成長ではなく「安定成長」と呼ぶべき、日本経済の底力を証明した時代だったわけですが、1980年代は、日本企業にとって「我が世の春」でした。自動車・家電などのメード・イン・ジャパン産業が世界で躍進し、株価と不動産価格の急騰によるバブル経済、1985年のプラザ合意による円高が特徴的ですが、後半にはコンビニの躍進、ブランドブーム、専門店やショッピングモールが成長し、対照的にデパートやスーパー、零細小売店など既存小売業の伸び悩みや衰退が始まります。
1980年代の最大の特徴は、1970年代に比べて危機感が決定的に欠如していたことです。1970年代はオイルショックという危機があり、経営者も労組も必死に対応していました。その結果として日本的雇用調整が功を奏し、日本的経営が世界的に注目されました。しかし1980年代になると、前述のように『ジャパン・アズ・ナンバーワン』といわれて、日本人は本当に調子に乗ってしまいました。第1次大戦前までのパクス・ブリタニカ(イギリスの時代)、第1次大戦後のパクス・アメリカーナ(アメリカの時代)を経て、パクス・ジャポニカになったと考える経済学者や経営者も多かった。「ミスター臨調」と呼ばれた土光敏夫氏だけは危機を叫んでいましたが、全体としてこの危機感の欠如こそ1980年代を特徴づける最大のポイントです。
当時の日本の経済的地位はそれほどに高かった。
たしかに数字上は圧倒的でした。1989年の世界の時価総額トップ50社のうち、NTTを筆頭に、金融機関など32社が日本企業でした。これを支えた条件として、まずエネルギー価格が下がったことが挙げられます。1970年代は石油価格が異常に上昇した時代でしたが、1980年代に入ると、原油価格が下落するとともに1970年代に日本が進めた脱石油政策が花開きました。
たとえば天然ガスはパイプラインで運ぶものでしたが、液化してLNG(液化天然ガス)の形で、船で運べるようにしました。これは公害対策で1969年に東京ガスが東京電力と一緒に始めたのが最初で、1970年代に根付き、エネルギー源として本格的に使えるようになりました。
海外炭の利用についても、石炭は重く、水分や灰分を含むため輸送費がかかり、貿易には向かなかったところを元首相の田中角栄氏などが頑張って、オーストラリアやインドネシアからの海外炭の大量輸入を実現させました。なお、石炭は、いまでも基本的に採掘地の近くで地産地消するのが常識です。日本では、1978年に長崎県の松島火力発電所にJ—POWER(電源開発)が世界初の本格的な海外炭火力発電所を建設しました。
このように、電力では、原子力、LNG火力、海外炭火力の3つのエネルギーを使い分けることができました。折しも、石油価格が1バレル32ドルから10ドル程度まで下がってきました。加えて、1985年から為替が円高に振れたため、円ベースでの輸入価格がさらに下がり、日本経済繁栄の基本条件が整ったのです。
日本が脚光を浴びる時代になった。
日本製品が世界にあふれるようになりました。円高になれば、貿易収支上、不利になるはずですが、それでも競争力を維持できるくらいに勢いがあった。ですが、これがジャパンバッシングを招きます。この影響もあって、1981年から米レーガン政権下で日本車の輸出自主規制が始まり、アメリカ側が日本車の輸入を事実上制限しました。その結果、日本企業はアメリカへの直接投資を本格的に始めます。
その先駆けとなった企業は。
ホンダだけが自主規制が始まる前の1979年にオハイオ州メアリーズビルに進出していました。円安で輸出が有利だった時代に海外直接投資を始め、しかもアメリカに建てた工場は日本の工場より大きくなったのです。さらに早かったのがソニー(現ソニーグループ)です。ソニーがカラーテレビ工場をサンディエゴに建てたのは1971年、まだ1ドル360円の時代でした。「アメリカ人が観るテレビはアメリカで生産しなければならない」というソニーの哲学があった。この時代のソニーとホンダの先見性には、やはり特筆すべきものがありました。
1984年にトヨタ自動車とゼネラルモーターズ(GM)がカリフォルニア州フリーモントに設立した合弁会社NUMMI(ヌーミ)も象徴的ですね。
のちにテスラの工場となった場所ですね。輸出規制を回避する日本企業の海外直接投資(FDI)の一環で、トヨタにとって初の北米生産拠点でした。トヨタ生産方式をGMに教えたことで、結果的に日本的な生産システムが世界に伝わった。『ジャパン・アズ・ナンバーワン』の実証でもあったのです。1989年にマサチューセッツ工科大学の研究者などによってまとめられた、アメリカ製造業の再生を期した『Made in America』(草思社)でも「日本に学べ」と述べられており、リーン生産方式と呼び方を変えていますが、そのカギこそトヨタ生産方式であると記しています。トヨタの社名は使いたくないから、「リーン生産方式」と改めたのです。
トヨタは海外生産を始めた時、レクサスという別ブランドを展開しました。ホンダはアキュラというブランドをつくりました。これらは成功しましたが、逆に失敗したのが日産自動車です。ダッツンあるいはダットサン(DATSUN)という名前でピックアップトラックなどを輸出しましたが、これをニッサンに変えたのが失敗でした。「そんなブランドは知らない」と信頼を獲得できなかったのです。
当時のソニーについてはいかがでしょうか。
1970年代の話になりますが、ソニーのビデオカセットテープの規格、ベータマックス(ベータ)について触れないわけにはまいりません。ベータは画質がクリアで優れた製品でしたが、それを家庭用のビデオ録画用に販売した際に、アメリカのテレビ番組制作者側から著作権侵害だと大規模な訴訟を起こされた。それに対してソニーが中心となって「タイムシフト」という概念を持ち出し、同じ番組でも放送と同時に観るのと録画して別の時間に観るのでは違う商品であるという論法で、法廷で勝利しました。これがなければビデオテープレコーダーという製品自体が潰れていたでしょうし、その後のアップルなどのビジネスも生まれなかったでしょう。そのくらい革新的なことを当時のソニーはやっていたのです。
ただし規格競争では、ご承知の通りベータはVHSに負けました。この時点では、単に、日本ビクターやパナソニックという同じ日本勢に負けたにすぎなかったのですが、素晴らしい技術で、高品質の製品をつくっても、製品の優秀さを過信して、デファクトスタンダード(事実上の業界標準)を必ずしも獲得できるとは限らない。1990年代以降、同じような失敗事例が見られるようになりましたが、ベータvs.VHSはその先駆けだったと思います。
日本の国際的地位は一変しました。
1980年代の日本は、本当に我が世の春を謳歌していました。しかもどんどん円高が進み、GDP(国内総生産)が膨れ上がって1人当たりGDPが世界上位となり、さまざまな世界ランキングでもトップになります。これは円高効果によるところが大きかった。
FDIなど新たな展開がありましたが、実際には、根本的な競争力の構築には至りませんでした。「追い付け、追い越せ」の時代が終わり、トップに立ったと思った瞬間から、絶えざる改革への意欲が失われてしまったのです。この慢心こそが、1990年代以降の長期停滞につながる最大の要因だったと、私は考えています。
1980年代は日本がピークを迎えながらも、同時に慢心の時代でもありました。1970年代の危機感と必死の対応が成果を上げ、世界からの評価も高まったものの、その成功が逆に危機感を失わせることになったのですね。
危機に強かった日本が、成功によって危機対応力を失ってしまったという皮肉な結果でした。教科書ではプラザ合意を転換点として語られますが、本来はプラザ合意には日本が国際競争力で戦っていく場が整ったという意味があった。それを活かせなかったことがはっきりしたのは、続く1990年代です。欧米へのキャッチアップを考えている間は危機感の効果が続くものです。慢心が一番の敵なのです。