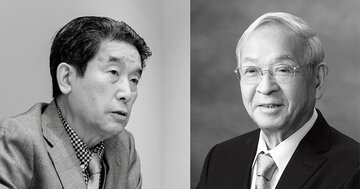1990 to 1999
部分的な危機を全体の危機と
誤解した時代
1990年代は、バブル崩壊、不良債権処理、山一證券・北海道拓殖銀行の破綻といった暗い話題から始まり、その後も、失われた10年、リストラ、就職氷河期、デフレ経済、ゼロ金利政策などが話題になりました。一方、IT革命やベンチャーブームによる新たな成長機会も生まれ、2000年代のデジタル経済への転換の土台が築かれました。
大半の日本人が気づいていない点でもあり、重要なことは、1990年代の危機は「部分的」だったことです。全体が危機に見舞われたわけではないのです。生産・製造は健在で、実際貿易黒字は1990年代を通じて増え続けていました。
問題だったのは、不良債権という言葉に象徴されるように、日本の金融システムが壊れてしまったことでした。このように部分的な危機であったにもかかわらず、全体的な危機だと見誤り、日本中がパニックに陥ったことが最大の問題でした。
本来、日本は1930年代も1970年代も危機を乗り切る力が高く、島国でありながら、まがりなりにも世界で闘っていた。にもかかわらず、1990年代の危機では、これまで幾度も危機を乗り越えてきたという日本人の強みが忘れ去られてしまった。それこそ明治維新以来の近代史上初めてといえる、極めて衝撃的な出来事でした。
背景には何があったのでしょうか。
一番大きかったのは土地投資です。景気が悪化し始めた1980年代後半くらいから財テクが流行り、それが企業努力であるかのようにまかり通っていた。戦後、景気には波があっても、土地価格だけは一度も下がらず、ずっと右肩上がりでした。土地を担保にして貸し出す、あるいは土地へ投資することには絶対に失敗がないということで、企業は苦しくなると、まともな生産・製造体制が整っている企業までが、不動産投資に流れ、社内で出世するのも財テク担当でした。それが、東京の商業地価で5分の1まで下がったわけですから、バブル崩壊のダメージは相当大きかったといえるでしょう。
この時、日本企業は勘違いしてしまった。つまり「過剰な投資」ではなく、「過剰な不動産投資」が問題だったのに、投資自体がだめだと総括してしまった。ですから、投資は抑制すべしという短絡的な結論に走り、ソニーやホンダも含め、すっかり自信を失ってしまいました。
日本が1990年代に凋落したのは、アメリカ西海岸から来たICT革命によるブレークスルーイノベーションと、最初は台湾、韓国、香港、次いで、中国本土からやってきた破壊的イノベーションとによって挟み撃ちされた結果だといえます。このうち、後者の破壊的イノベーションという概念は、クレイトン・クリステンセンが1997年に発表した『イノベーションのジレンマ』(翔泳社)の中で、打ち出したものです。端的に言うと日本では、技術や事業への投資がなおざりにされたということです。
そのように自信を失った結果、「日本的経営はダメだったのではないか」という間違った反省が幅を利かせ、アメリカ的なガバナンスが重視され始めました。彼らに倣ってKPI(重要業績評価指標)も、ROA(総資産利益率)やROE(自己資本利益率)、ROI(投下資本利益率)などに置き換わり、これらの数値を向上させることに血道を上げるようになります。
アメリカ企業のROEやROAが上昇したのは、大きな事業投資によって分母のエクイティとアセットを増やしながら、優れたビジネスモデルが奏功して分子のリターン(利益)がそれらを上回るペースで増大し、結果的にROEもROAも上がったからです。Windows95でIT革命を牽引したマイクロソフトもしかり、こういう好循環こそ健全な姿なのです。
ところが日本企業は、事業投資をなおざりにして、ROEやROAを上げようと、分母のエクイティとアセットを減らすという、とんでもない方向に走ってしまったわけです。いま思えば、そうした投資抑制の象徴が日産CEOだったカルロス・ゴーン氏です。
ゴーン氏の経営手法についてはどう評価されますか。
自社株買いによる償却や借金の返済でエクイティやアセットを減らすと、短期的にはV字回復し、ROEやROAは上がります。しかし、投資を控えているので長期的な競争力を失い、日産はトヨタとの間に挽回不可能な差をつけられてしまった。私はゴーン氏が盛んに礼賛されている頃から投資抑制は感心しないと指摘してきました。その後ゴーン氏が特別背任罪に問われるに至り、いまでは「水に落ちた犬を打つ」形になってしまうので、批判しにくくなってしまいましたが(笑)。
同様の例が電力会社です。東京電力第8代社長の荒木浩氏が徹底して投資を抑制した。エビデンスを示すことは難しいのですが、私は、そのことが福島の原発事故の遠因の一つだったと考えています。というのも、削減したのが、保安投資と送配電投資だったからです。各電力会社ともこれに追随しました。これが日本の再生可能エネルギー事業の遅れにもつながることになりました。
株主重視の経営についてはいかがお考えですか。
株主重視自体が悪いわけではありません。問題なのは株主だけを重視することです。他のステークホルダー、特に従業員や顧客を大事にするところが日本的経営の長所だったのですが、それを脇に置いて株主重視というのはよろしくない。
株主への利益が最優先なのだと目先の利益だけ追うことで、投資を控えると、成長が止まり、結局株価が伸び悩んで、キャピタルゲインが得られなくなってしまうわけで、結果的に株主重視にもなっていないというはめになるのです。
1990年代にも雇用調整がなされましたが、1970年代のそれとどのように違っていたのでしょう。
1970年代と1990年代の雇用調整には決定的な違いがあります。1970年代の労組は雇用全体を守っていました。1990年代はまったく逆で、組合側も経営側も正社員は守るものの、非正規労働者はその対象外で、むしろ調整の対象にしようという考え方に変わってしまった。昔のレイオフに賛成したアメリカの労組に近くなり、日本の労組のよいところは縮小してしまいました。
その流れで、調節弁としての非正規雇用の数を増やし、業績が悪化すれば彼らを切るという「派遣切り」が一般化しました。これは、詰まるところエクイティやアセットを減らすのと同じ発想です。
1990年代にリストラという言葉が広まった時、リストラ=首切りという意味に取り違えられ、いまもそのように使われています。リストラクチャリングとは、正しくは構造改革なのですが、誤用されたリストラ(=首切り)に労組は反対しなかったわけです。