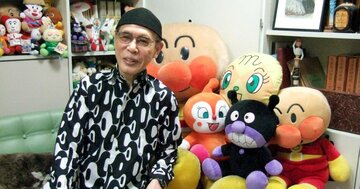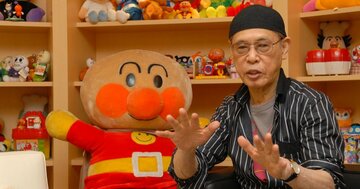これらの書物を次から次へと読んでいった経験があれば、学生向けに書くための素地としては十分のはず。クラスで回覧する雑誌も編集しており、そこでは小説を書くという旺盛な仕事ぶりを見せます。伯父に反対され叶いませんでしたが、早稲田大学に入学して大作家になるという夢を持っていたやなせ先生は、文才に自信があったのです。後年、様々な分野で活躍したやなせ先生の原型が、この時すでに見られるようでもあります。
井伏鱒二と太宰治に出会い
やなせたかしの文体が変わった
井伏鱒二と太宰治に心酔した経験もまた、その原型を語るうえで欠かせません。
当時、やなせ先生の文体は古めかしい美文調でした。父と伯父が所有していた古典的な本を読み過ぎた結果でしたが、どうしてなのか、ある時からこの文体が原因で筆が進まなくなってしまいます。
そんな時、やなせ先生の文体を解きほぐしたのが井伏鱒二と太宰治の作品でした。やなせ先生は、2人の文体から詩のリズムを感じ取り、文章の書き方が分かったのだと語ります。井伏鱒二の『山椒魚』『屋根の上のサワン』や、太宰治の短編集『晩年』などに深い感銘を受けたとも話しています。
井伏鱒二と太宰治の短編小説を読むと、やなせ先生が2人から大きな影響を受けていることがよく分かります。塩をかけることで引き立つスイカの甘さのように、小説に漂う哀愁はメルヘンの美しさを際立たせ、そして美しいメルヘンの世界が哀しみをより深くする——この相反する2つが組み合わさった作風は、やなせ先生の作品にもよく見られるものです。
『晩年』に収録された太宰治の短編小説「魚服記」もまた、そんな組み合わせが見て取れる作品です。
同作の主人公は、小さい茶店で店番をする娘のスワです。その茶店は、滝壺の近くの山小屋で炭焼きをする父がこしらえたもので、2人はそこで年中寝起きをしています。かいがいしくも、スワは稼ぎを補うためキノコ採りをする一方、父は炭やキノコが良い値で売れると、きまって酔っぱらって帰ってきます。
ある日、スワは父からむごたらしい仕打ちを受けます。そしてスワは、外へ飛び出していき、滝に飛び込んでしまうのです。