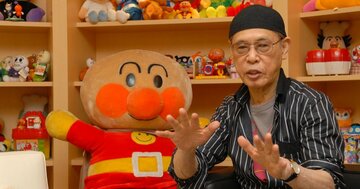軍隊が作成した身分調査票に「軟弱にして気迫に欠ける。男性的気性の養成を要す」と記されていたように、誰から見ても軍人とは程遠かったのです。
そんな軟弱にして気迫に欠ける男は、不運なことに小倉の西部73部隊に入隊が決まります。同部隊は勇猛果敢で知られていて、野武士みたいな人たちが集まっていたのです。入隊後、やなせ先生は猛訓練を受けるとともに、野武士から殴られまくる日々を送りました。
ところが、意外にもやなせ先生はたくましさを見せます。時間が経つにつれ軍隊生活の要領を覚えてしまい、しっかりと順応してしまいました。そのうえ厳しい軍隊生活について「しかしぼくのようにどうしようもない人間には、かえってよかったかもしれません」とまで述べてしまいます。
入隊して数カ月後、幹部候補生の試験に合格します。やなせ先生の学力を考えれば当然の結果ですが、試験前日の仕事中、居眠りをしていたことがばれてしまい、合格して「甲幹」になるはずが「乙幹」に繰り下げとなってしまいます。乙幹は甲幹より偉くなれないので、やなせ先生はがっかりしたようです(編集部注/甲種幹部候補生は少尉、乙種幹部候補生は軍曹まで昇進できた)。
前途洋々だった者たちの死に思う
「ぼくは何をしたらいいのだろう」
しかし、人間万事塞翁が馬。幸運は不運を呼び、不運は幸運を呼ぶのかもしれません。甲幹に合格した隊員たちは、満州や中国の戦線に送られてしまったのです。結果として、居眠りという名の偶然がやなせ先生の命を守ることになりました。
なぜ戦友は死んでしまい、どうして自分は生き残ってしまったのだろう。戦中派が残した文章には、こうした苦悩に満ちた言葉がよく見られます。些細な出来事で生死が分けられてしまう環境に身を置くことで、生きるも死ぬも偶然が決めるという感覚が染み付いてしまったのだと思います。
運悪く死んだ優秀な戦友には、輝かしい未来が待っていたはず。汗を流して働き、この社会をよりよきものにしたに違いなかったはず。それが果たせなかった彼らのために、いったい自分は何ができるのか。彼らの代わりに、どうやって生きていくべきなのか——重い十字架を背負い続けた戦中派は数多くいて、そのなかにはやなせ先生も混ざっています。そして、才に恵まれた優秀な弟・千尋は、海軍の特別任務により戦死してしまうのです。