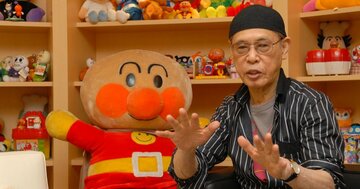後年、やなせ先生は弟に対して詩を残しています。
亡父の墓石に水をかけ
伯父の墓石に水をかけ
伯母の墓石に水をかけ
そして弟の墓石に水をかけ
ためらいがちにぼくは聞いた
「いったい君は
何をしたかったのだろう
君のかわりにやるとすれば
ぼくは何をすればいいのだろう」
おもいでの中の弟は
まだとてもちいさくて
びっくりしたような眼をみひらき
「兄ちゃん、わからないよ」
と恥ずかしそうにいった
(やなせたかし著『やなせたかしおとうとものがたり』フレーベル館、2014年)
自分が年老いていくほど、記憶のなかの戦死者はますます若く感じられます。年月が過ぎるほど、十字架が重くなってしまうのも仕方がありません。それまで戦争について語りたがらなかったにもかかわらず、晩年になってやなせ先生が堰を切ったように書籍として残しはじめたのもまた、重い十字架を下ろす作業だったのかもしれません。
福建省ののどかな農村で
「日本の正しさ」を宣伝せよ
1941年12月8日、日本が米英に宣戦布告したことで、やなせ先生の軍隊生活は延長になってしまいます(編集部注/徴兵された陸軍兵の満期は2年だった)。それまで通り、小倉で暗号解読の任務に従事することになりました。
1943年、ついに戦地である中国・福州(現在の福建省)に上陸する日がやってきます。「明朝は敵前上陸だ」という号令を聞き、やなせ先生も覚悟を決めました。
ところが、上陸してみたものの敵兵は見当たりません。農村風景が広がるのみです。それどころか、現地の住民は、今が戦争中だということさえ知りませんでした。命を捨てる覚悟を決めたわりには、随分と穏やかな日々が待っていたわけです。もちろん、いつ敵が襲ってくるか分からないという緊張感はあったものの、他の戦地に比べれば雲泥の差でしょう。
上陸後、暗号班の仕事は暇だったので、やなせ先生は宣撫班の仕事を手伝うことにしました。ここでの宣撫の仕事とは、現地の中国人に対し日本の正しさを説明することです。つまり、占領地である福州を安全に統治するための宣伝工作です。ただし、やなせ先生は、この日本の戦争は間違いなく正しいと信じていたので、これが宣伝「工作」であるとは少しも考えていませんでした。