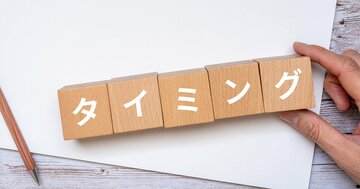一方で、遠くのカップを先に選択した参加者は、「効率的な方を選んだ」と回答していました。ちなみに、効率的かどうかをどれくらい「考えたか」ということと、ワーキングメモリの容量の個人差が関連しているという結果も得られませんでした。つまり、前倒しはその人が目の前のタスクを「考えるかどうか」によって決まるところが大きいというわけです。
自動的に前倒しをする人もいれば、効率を考えたうえで前倒しをしない人もいる。いたって当然のことのようですが、前倒しをしやすい人の特徴を探るうえでは、非常に有用な知見です。「考えること」を楽しむ人は前倒しをしにくいけれど、「考えること」を楽しまない人は前倒しをしやすいともいえるかもしれません。
考えることを楽しむのを放棄する、あるいは後のことを考えずに、ただ目の前にあるタスクから解放されるために矢継ぎ早に処理するのは、極端な前倒しといえるでしょう。この実験結果は、前倒しのし過ぎに警鐘を鳴らすものでした。
前倒しのしすぎが
無駄な仕事を生む場合も
前倒し自体は悪いことではありませんが、前倒しによって発生するコストがあまりに大きい場合や、タイミングとして明らかに最適ではない場合にも常に前倒しをするようであれば、注意が必要です。後のことを考えずに早めに着手することが、ときに新たなコストやトラブルを生んでしまうこともあります。
たとえば、冷蔵庫のストックをきちんと把握しないまま食料品の買い物に行けば、帰宅後に「まだあったのにまた買ってしまった」「本当に必要なものを買ってこなかった」と気付き、後悔することがあるでしょう。普段から衝動的に買い物をする人であれば、その可能性は高まります。
また、夕食の後片付けをするシーンにおいて、翌日の朝のゴミ出しをしやすいように早々にゴミをきっちりとまとめておいたところでまたゴミが出て、早めにゴミをまとめ過ぎることのせっかちさを指摘される、といったこともあるでしょう。あげていくとキリがありませんね。