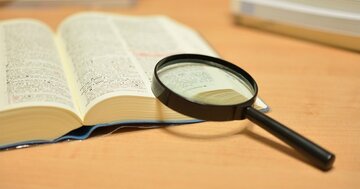前日の晩御飯を一緒にとった後、いつも通り、父親は自室へ入り、翌朝は、これまたいつものように、みんなが仕事や学校へと出ていったという。
学校から下校した子どもが、おじいちゃんの朝ごはんがそのまま食卓に置かれているのを不思議に思い、夕方になって部屋をのぞくと、亡くなっているのを発見したそうだ。
ここで紹介した2人の知人の家族の最期は、どちらもぽっくりだ。遺体は1日以内に発見されているとはいえ、同居する人はいるのに、死ぬ瞬間に立ち会った人は誰もいない。
また、病院で闘病中に亡くなったとしても、死ぬ瞬間に立ち会う家族がいるとは限らない。
「様子がおかしい」「亡くなりそうだ」という連絡を病院から受けても、家族がすぐに駆け付けられるとは限らない。そもそも患者の様子がおかしいことを病院が知るのは、医療者がそばにいてわかったわけではなく、患者が指につけていた、血中酸素濃度を測るパルスオキシメーターが、ナースステーションに異常を知らせたからにほかならない。
病院にいても、患者の死を見守っているのは医療機器であって、家族がベッドサイドを囲み、「おじいちゃん、ありがとう」と言った後に息絶えるというのは、ドラマだけの世界なのだ。
ひとり暮らしの高齢者の半分が
自分は寂しく死ぬと思っている
少し古いが、60歳以上を対象にした内閣府の「高齢者の住宅と生活環境に関する調査」(平成30年)によれば、「孤立死(誰にも看取られることなく、亡くなった後に発見される死)について、身近に感じますか」という質問に対し、「とても感じる」人が9.1%、「まあ感じる」人が24.9%と、高齢者の3割以上が、孤立死の問題を身近に感じていた。
これをひとり暮らし世帯だけについてみると、「とても感じる」が15.9%、「まあ感じる」が34.8%と、孤立死を身近に感じる高齢者は半数以上を占めた。
実際、誰にも看取られることなく息を引き取り、その後、相当期間放置される「孤立死」は増加している。警察庁の統計によれば、2024年1月から3月の3カ月間に、ひとり暮らしの自宅で亡くなった65歳以上の高齢者は全国で1万7000人程度いることが明らかになっている。