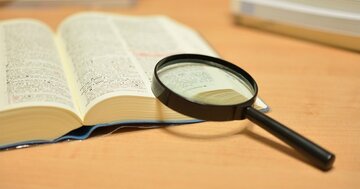自宅でお葬式をしなくなったことも、多死社会を実感しなくなった一因だ。(一般財団法人)日本消費者協会の全国調査によれば、過去3年以内に葬儀を出した人のうち、自宅で葬儀をした人は1985年には58.1%と過半数を占めたが、91年には52.8%、99年には38.9%、2007年には12.7%、2014年にはわずか6.3%にまで減少している。
最近では、家族数人でのお別れが増えたため、自宅で葬儀をするケースが散見されるようになったが、それでも、家族葬であっても葬儀会館を利用するのが当たり前となっている状況には変わりがない。
近所づきあいが希薄になれば、そもそも住んでいる人のことを知らないのだから、その人が亡くなったかどうかも知らないし、たとえ知ったとしても、三人称の死なので、お葬式に参列することもない。
その結果、たくさんの人が亡くなっている昨今の現状を多くの人は実感できなくなっている。
なぜ私たちは他人の死を
見世物にしてしまうのか
このように死が社会から隠蔽されている状況を、イギリスの文化人類学者であるG・ゴーラーは「死のポルノグラフィー化」と呼んだ。
例えば日本では、死について口にするのはタブーであると長らくされてきたが、周りの人の訃報を聞くと、「どうして亡くなったのか」、他人の死因が気になる人は多い。
つい先日も、配偶者を亡くした知り合いから、「死因について近所の人から根掘り葉掘り詮索されて、嫌だった」と、連絡をもらったばかりだ。
有名人が突然亡くなったことを報じるニュースが流れると、SNSには、死因を詮索する書き込みがあふれる。
パリやシチリアなどカトリック色が強い地域には、500年ほど前に作られた地下墓地(カタコンベ)が残っている。ミイラになった遺体や頭蓋骨は一般公開されており、世界中から観光客がやってくる。
エジプトのミイラ展が日本にやってくると、入場するのに何時間も待つほどの大人気になるし、2000年前後には、日本各地の博物館で「人体の不思議展」が開催され、話題となった。