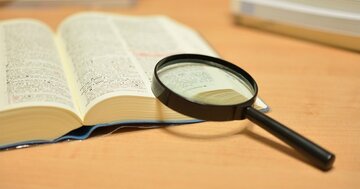現在の日本では子ども世代が定年退職を迎えてから、肉親との死別を経験するケースも当たり前になってきており、高齢になるまでは「死」を意識する機会がないこともある。
私は、立教セカンドステージ大学で18年間も講義をしているが、当初の講義は「現代の死と葬送」という名称だった。定年退職後に入学してきた人たちのなかには、「生きがいのあるセカンドライフを夢想しているのに、死についてなんぞ学びたくない」という学生が少なくなかった。
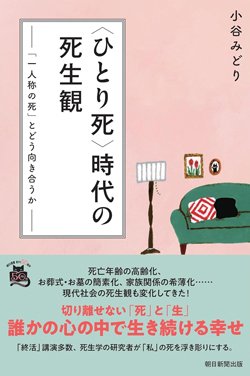 『〈ひとり死〉時代の死生観「一人称の死」とどう向き合うか』(小谷みどり、朝日新聞出版)
『〈ひとり死〉時代の死生観「一人称の死」とどう向き合うか』(小谷みどり、朝日新聞出版)
そこで次年度、事務室が「最後まで自分らしく」と名称だけを変更したところ、大勢の学生が興味を持ってくれるようになった。
寿命が延びると、死の不安よりも、長引く老後への不安の方が大きくなる。だから「死後の不安」よりも、「死までの生のあり方」を考えたいという人が多いのだろう。
さらには死者とのつながりが希薄化していることもある。祖父母と同居する
3世代世帯が減少すると、祖父母や両親が老い、病に倒れ、亡くなっていくというプロセスをそばで体感することはないので、「亡くなった祖父母は見守ってくれている」という感覚も薄れている。
自宅から遠い場所にあれば、先祖のお墓にお参りする機会が減り、死者とのつながりを意識することが少なくなれば、当然、自分の死を考えることもなくなる。