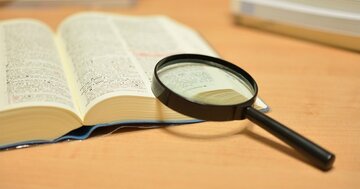先日亡くなった友人の妻は、完治が見込めない末期のがんであることは医師から告知されていたが、友人によれば、妻は、「自分が死ぬ」とは考えていないようだったということだ。
別の友人も、肺がんの末期であることを告知され、抗がん剤治療などの積極的治療を一切受けないことを決めたが、家族は、どんどん病状が悪化する友人と、深い話をすることはできなかったという。
患者本人が話さない限り、家族や親友は、病床にある人に対して、死についての話題をすることははばかられるからだ。これも、死のポルノグラフィー化のひとつの事例だ。
自分が大切な人より先に亡くなれば、大切な人との死別に運よく直面しないで済むだろうが、世の中には死なない人はいないので、一人称の死(編集部注/自分の死のこと)に無関係な人はいない。
しかし、フランスの哲学者で、死のイメージを人称別に論じたジャンケレヴィッチは、自分の死は自分では体験できないことを、「わたしはわたし自身にとってはけっして死なない」「わたしがある限り死は不在」と表現した。
みんな、「自分もいつか死ぬ」ことは頭ではわかっているものの、自分が死ぬ瞬間を自分では体感できない。
江戸時代に庶民に人気があった狂歌師、大田南畝は、「今までは 人のことだと 思ふたに 俺が死ぬとは こいつはたまらん」という辞世の句を残しているように、「自分の死」についてどこか他人事のように感じる人は、昔から少なくなかったようだ。
死を見なくなった日常が
自分の死を遠ざけていく
現在の日本のような多死社会にあっても「自分の死」を意識しない理由は、死のイメージの隠蔽による「死のポルノ化」だけではない。寿命が延びたことによって、死が先延ばしされ、自分の死を意識しなくなっていることもある。