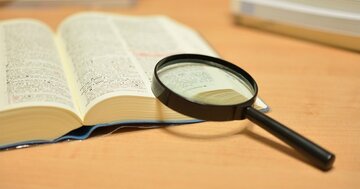私も足を運んだことがあるが、実際の遺体にプラスティネーションという樹脂加工を施し、さまざまなポーズをとった標本が陳列されており、なかには標本の輪切りや、内臓だけを取り出した展示もあった。
これが本物の遺体や内臓だと思うとグロテスクだったし、故人の気持ちになれば、こんな格好をさせられ、陳列されることを気の毒だなあとも思った記憶がある。全国で開催されたこの展覧会には、のべ980万人が来場したという。
しかしこの展示会は、遺体を商業目的で不特定多数に公開したこと、また遺体が尊厳ある扱いを受けていない点が問題視され、のちに物議をかもした。
2009年には、フランスのパリ大審裁判所は、「人体の不思議展」は人権侵害として、パリで開催予定だった展覧会の中止の判断をしているし、2018年にはスイスのローザンヌ市で展覧会がおこなわれていたが、「中国で拷問され処刑された受刑者の遺体が含まれている可能性がある」として開催が中止された。
日本でも、2010年に新潟県で「人体の不思議展」がおこなわれることになった際、新潟県保険医会が開催中止を求める声明を発表したが、開催は決行され、来場者は5万人を超えた。
他人の死には敏感なのに
自分の死からは目を背ける
タイのバンコクにある法医学博物館には、ホルマリンに浸かった赤ん坊の遺体のほか、列車事故で亡くなった人、自死、射殺などの遺体の写真、ヘビースモーカーだった人の肺などが陳列されている。観光ガイドブックにも掲載されているので、訪れる日本人観光客も少なくない。
こうした「死」をイメージするモノや情報はタブーとされている反面、他人の死については、「見たい!」「知りたい!」という気持ちがあるのもまた事実である。こうした状況を、ゴーラーは「死のポルノグラフィー化」と呼んだのだ。
親しい家族であっても、死にゆく人と残される側との間で、ざっくばらんに死について語り合えるケースは多くはない。