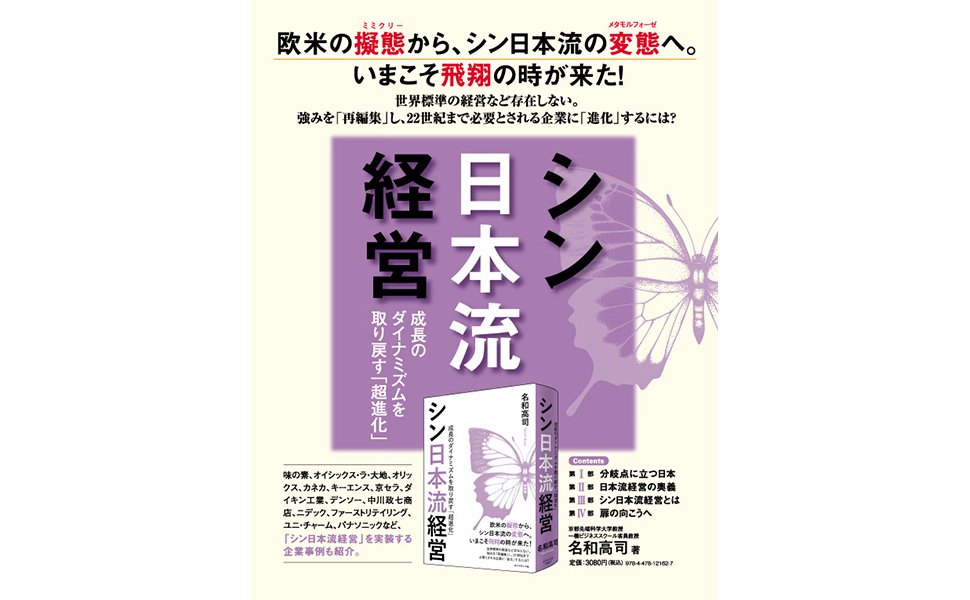新規事業開発においても、それを0→1に終わらせず、1→10、10→100へとスケールさせる仕組み。リクルートはそれを「10のメソッド」として方法論化することによって、10倍を超えるPBRを実現している(2024年12月末現在)。
あるいは事業のポートフォリオを「ずらし」続け、それらを「つなぐ」ことで、新たな価値を生み出す組織能力。これも本連載で取り上げたカネカが、四半世紀にわたり、磨きをかけていった、同社「ならでは」の仕組みである。
※詳細は本連載の記事『日本の老舗化学メーカー発「意外な商品」がアフリカ人女性に大ウケ!その正体とヒットの理由とは?』をご参照ください。
いずれもカギとなるのは、仕組みそのものではなく、それを進化させ続ける動的能力である。そのような動的能力に基づく経営こそが、学習優位の本質であることは、何度も繰り返してきた通りである。
名和教授が伝授!
企業の組織能力を算出する「数式」とは?
これら3つの必要条件を、簡単な数式で示すと次の通りとなる。
組織能力=αβΣ(P)
まず後半のΣ(P)は、一人ひとりの人財(P)の総和を表している。この数値を高めるためには、第一の要件である「求心力」がカギとなる。「シン和力」と名付けたパワーである。そしてαがソフトパワー、βがハードパワーだ。これらはいずれも、人財のパワーの総和を、さらに10X化していくブースターである。
組織能力は、これら3つの必要条件の乗数効果となって表れる。それを「シン乗数力」と呼ぶことにしよう。乗数なので、どれか一つでも小さくなれば、組織能力全体が大きく逓減する。逆に、それぞれを高められれば、全体を大きくスケールアップさせることができる。経営者が本気で取り組むべきは、一人ひとりの人財開発ではなく、このような組織開発である。
個を磨き上げるのではなく、有機体全体のパワーをいかに高め、それをいかに全開にしていくのか。その問いかけに答えを出し続けていくことこそ、シン日本流経営の真髄である。