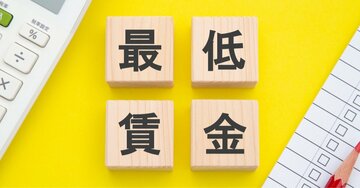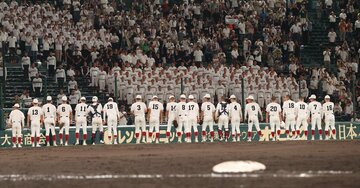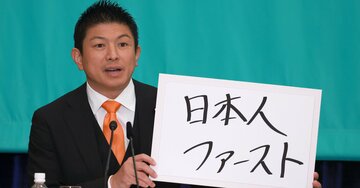一見当たり前のことのように思えるが、戦争の本質を19世紀に論じた有名な著書「戦争論」でクラウゼヴィツも「戦争とは外交の延長である」と書いているように、少なくとも第一次世界大戦が始まるまでは、戦争とは国家指導者がとりうる政策の選択肢と考えられていた。
従って他国に攻め込む戦争をした指導者も、そのこと自体で責任を問われることはなかった。だが、国家の総力戦となった第一次世界大戦の惨禍であまりにも多くの人が亡くなったため、大戦後に、戦争の違法化、すなわち戦争を起こしてはいけない、という国際法を作ろうという機運が高まり、1928年に戦前の日本も参加して「パリ不戦条約」が結ばれた。そこには「戦争を放棄する」と書かれており、現在の日本国憲法の第九条も、この不戦条約の文言を取り入れている。
ところが、パリ不戦条約は、戦争をしないことを国家に義務付けたものの、指導者個人の責任に言及することや、条約に違反した場合の制裁措置までには踏み込んでおらず、宣言的な性格の濃い条約だった。
この条約の考え方をさらに「発展」させて戦争指導者個人の犯罪として裁こうというのが東京裁判の「平和に対する罪」で、画期的なものだった。ところが、法の世界で、「発展」とか、「画期的」ということは落とし穴になることがある。
法とは、それが制定された後にのみ適用されなくてはならず、制定前の行為に遡及して裁くことはできない、という原則的な考え方がある。これに反して法の制定前の犯罪をその罪で裁くことを「事後法」と言い、やってはいけないこととされている。パル判事がついたのはまさにこの点だった。
東京裁判の最大の「売り」である、「平和に対する罪」は戦争が終わった後に導入されたもので、不完全なパリ不戦条約を無理やり根拠にした事後法であり、第二次大戦での指導者の行為に適用することはできない。従ってその罪に問われている東条英機以下日本の指導者たちは全員無罪だ、と主張したのだ。