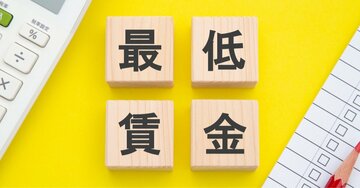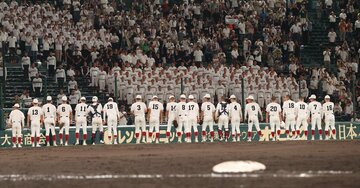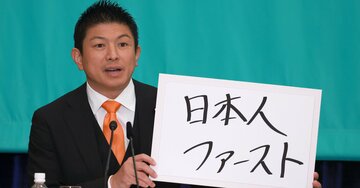パル判事のこの意見は、空前絶後のこの一大国際戦争裁判の根底を否定する究極のちゃぶ台返しと言えるもので、11人の判事団を大混乱に陥れ、以後、判事たちは互いに激論、説得、恫喝、疎外、圧力、理解、別れ、妥協、反発などを繰り返す2年半の間に、ありとあらゆる「あの戦争」をめぐる問題点が洗い出され、議論が重ねられていった……。
その事の顛末こそこのドラマの主題なので、ぜひ番組を見ていただきたいが、裁判がたどり着いた結論は、「平和に対する罪」を認め、前述のように被告全員を有罪とする、というものだった。
しかし、それは判事たちの「多数派」の結論にすぎず、公式判決のほかに5つもの「個別意見書」が出された。特にパル判事が提出したものは公式判決より長い膨大さという、激論の混乱がそのまま表に出た結末となった。
この点、ナチスを裁いたニュルンベルク裁判で少数意見はなかったこととは異なる。ナチスという絶対悪を裁くことと、満州事変から日中戦争、東南アジアへの進出から対米戦争へと複雑な経緯をたどり、最後にはソ連の参戦を招いたという日本の戦争を裁くことは事情が全く違った、ということでもある。そのこともドラマは描き出している。
それでは、80年近く前に、11人の判事たちが格闘したこの問題、「人は戦争を裁けるのか」を21世紀の私たちは克服しているのだろうか?
いまだにこの問題は、人類の課題としてまさに私たちの目の前にあるのだ。
私は制作者として、このドラマの第四話、最後のシーンの近くで裁判を終えて全判事の記念写真に向かう、多数派のリーダー格イギリス代表のパトリック判事と最年少でもあったオランダ代表のレーリンク判事との会話で次のようなセリフを入れた。
レーリンク判事「それは、オランダにあると良いかもしれません」
それは対立してきた二人が最後に和解する、という和やかな会話だった。だが、のちの歴史で、日本の戦争を裁くために臨時に作られた東京裁判の意志を継ぎ、世界各地で人類が果てしなく続ける戦争を裁くために、恒久的な裁判所がオランダにできる、という史実を当時の彼らも予感していた、という意味のセリフでもある。