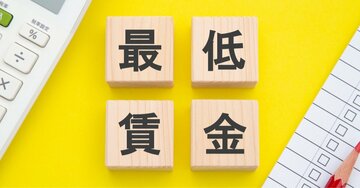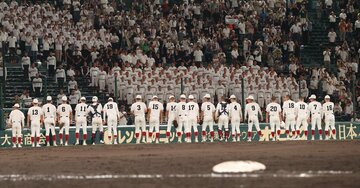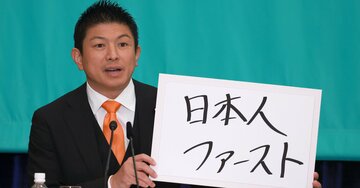ICC条約の締約国は現在、日本を含めて125カ国であり、国連加盟国の193カ国と比べれば少ない。つまり、まだまだ全世界的な組織にはなっていないということである。
何より決定的なのは、国際情勢を語るうえで絶対にはずすことができない大国であり安保理常任理事国でもある米・ロ・中、さらにはインドといった地域の大国も参加していないことだ。
その存在地がオランダであることに象徴されるように、ICCが信奉する「国際法」が西欧偏重の考え方であり、これまでの歴史で植民地主義を行ってきた彼らの傲慢さが今でも残っているのではないか?本当に国際的な価値観を体現するというのならば、アジアやアフリカで育ってきた、犯罪者への断罪を求めるだけではない和解のプロセスや文化的背景も大切にしているのか?といった疑問もある。
これらは、東京裁判でインド出身のパル判事が、欧米中心の多数派に反旗を翻したときから繋がっており、今も未解決の問題なのだ。
そして何より、戦争を起こした指導者を裁けるのか、つまり「人は戦争を裁けるのか」という命題は80年近くの時を経た今も解決されていない。
東京裁判の「平和に対する罪」は、その後「侵略犯罪」と名を変えて、ICCが取り扱う犯罪の類型の一つとして取り入れられている。
他の罪の類型、たとえば戦場での残虐行為などは締約国間の合意があり、すでに有罪判決を出すなど実績を重ねている。だが、侵略戦争を起こした指導者を裁く「侵略犯罪」については、締約国の間でもまさに東京裁判同様の喧々諤々の議論が続き、現在では極めて強い制限のかかった状態でしか合意がとれていない。
ましてや米・ロ・中のような非締約国の指導者に「侵略犯罪」を適用することは除外している。それどころか、締約国の中にあっても「侵略犯罪」の実際の適用(管轄権の行使を可能にする改正規程)は受け入れていない国も多く、受け入れている国は47カ国にすぎない。ちなみに日本も現在受諾していない。もし受諾すれば、あくまで理論的にではあるが、日本の首相や防衛相、自衛隊の幹部なども将来、侵略犯罪に問われる可能性を覚悟する、ということになる。