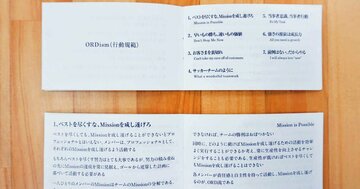Photo:Liubomyr Vorona/gettyimages
Photo:Liubomyr Vorona/gettyimages
京都先端科学大学教授/一橋ビジネススクール客員教授の名和高司氏が、このたび『シン日本流経営』(ダイヤモンド社)を上梓した。日本企業が自社の強みを「再編集」し、22世紀まで必要とされる企業に「進化」する方法を説いた渾身の書である。本連載では、その内容を一部抜粋・編集してお届けする。今回は、名和教授がシン日本流経営の好例として評価するメガベンチャー「オイシックス・ラ・大地」(2000年創業)の経営およびマネジメント術について深堀りする。同社の代表取締役社長・高島宏平氏は、やる気のない社員に対して「基本的には何もしない」という。その意外な理由とは――。
東大・マッキンゼー出身の起業家が
立ち上げたオイシックスの強みとは?
オイシックス・ラ・大地は、日本におけるCSV(Creating Shared Value)経営の先進企業である。CSVは、社会価値と経済価値の両立を指す。より平易に言えば、社会課題を解決することで収益を上げることを目指すものである。
ただし、これは簡単な話ではない。そもそも社会課題は、需要としては顕在化していても儲からないから供給が現れず、社会課題として放置されているのである。たとえば、SDGsが掲げる17の社会課題リストは、通常の事業としては「儲からない」リストにほかならない。
したがって、社会課題に取り組むには、異次元の創意工夫と覚悟が求められる。オイシックス・ラ・大地の創業者であり代表取締役社長を務める高島宏平氏は、筆者との対談の中で、「経営理念(パーパス)は、モチベーションの源泉を言語化したもの」でなければならないと語る。そして「自分たちは、何のためだったら頑張り続けることができるだろう?」と考えて「食の課題」に取り組むことに決めたという(※注)。
・高島氏の「高」の表記は、正確には「はしごだか」。
・高島氏は東京大学で情報工学を専攻後、マッキンゼーを経てオイシックスを創業。筆者がマッキンゼーで学卒採用責任者を担当していた際、採用を即決した経緯がある。詳しくは本連載第9回を参照。
・本稿で紹介している対談記事は、コスモ教育出版の月刊誌『理念と経営』2023年8月号「巻頭対談・本気で会社を変えたければ、まず社長が自らを改革せよ」。
オイシックス・ラ・大地は、「食に関する社会課題をビジネスの手法で解決」することを、企業理念に掲げている。ここでカギとなるのが、「ビジネスの手法」である。同社の場合、大きく2つある。イノベーションとM&Aだ。
まずはイノベーション。とは言っても、技術革新ではない。産業構造の革新を通じて、新たな市場を生み出すことである。オイシックス・ラ・大地は、「農と食のイノベーション」に取り組んでいる。農業と食品加工、さらに小売りまでを、「異結合(クロスカップリング)」させる。最近では、消費者から生産者へとつなぎ直す「アップサイクル」モデルにも取り組んでいる。
 PHOTO (C) MOTOKAZU SATO
PHOTO (C) MOTOKAZU SATO京都先端科学大学 教授|一橋ビジネススクール 客員教授
名和高司 氏
東京大学法学部卒、ハーバード・ビジネス・スクール修士(ベーカー・スカラー授与)。三菱商事を経て、マッキンゼー・アンド・カンパニーにてディレクターとして約20年間、コンサルティングに従事。2010年より一橋ビジネススクール客員教授、2021年より京都先端科学大学教授。ファーストリテイリング、味の素、デンソー、SOMPOホールディングスなどの社外取締役、および朝日新聞社の社外監査役を歴任。企業および経営者のシニアアドバイザーも務める。 2025年2月に『シン日本流経営』(ダイヤモンド社)を上梓した。
そして、顧客の「声にならない声」を聴く。高島氏自身、既顧客より「未(潜在)」顧客を家庭訪問して、ディープ・インタビューをすることを大切にしているという。顧客が潜在的に抱えている課題や、「こんなことがあったらいい」という未実現の夢を見つけることができれば、新たな市場創造の切り口が得られるからだ。
「1時間お話しして成果があがらなくて、帰りがけにポロッと口にしてくれた思い付きが、とても大事なヒントになることがあるんです」と、嬉しそうに語ってくれた。