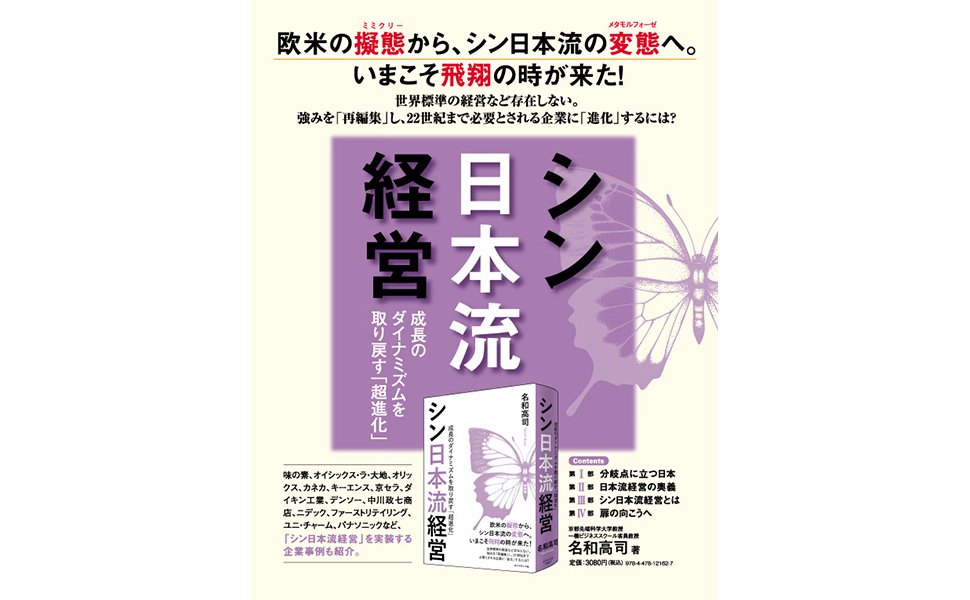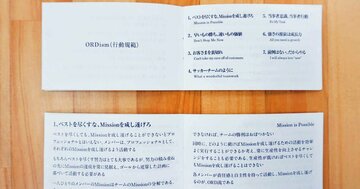高島氏が、やる気のない社員に
「あえて何も指導しない」意外な理由
では、企業が非連続な進化を遂げていく中で、リーダーはどうあるべきか。独自のマネジメント術の一端が、先述した対談に示唆されている。その一部を引用しよう。
高島 そもそも、オイシックスは採用に際して「セルフモチベーション(自分でモチベーションを上げる)ができる人」を選ぶようにしています。それは重要な採用基準なので、体感してやる気に火がつかないような社員はほとんどいないはずです。
そういう社員がいたとしても、基本的には何もしません。というのも、オイシックスのマネジメントの基本方針は「動機づけできない社員に時間とエネルギーを費やすより、エースを超エースにすることに費やせ」だからです。そのほうが組織の勝率は上がるので……。
名和 「2:6:2の法則」というものがありますね。あらゆる組織で、上位2割が成績優秀者、6割は平凡、残り2割が成績不振者に分かれるというものです。普通のマネジメントは、「上の2割は自走できるから放っておこう。自走できない下の2割を伸ばそう」としがちです。でも、御社は逆なんですね。
高島 はい。下の2割を底上げしても、組織全体としてはあまりハッピーにならないですから。それより、上位2割がさらに頑張って道を切り拓いてくれたほうが、結果的に下の2割が活躍する場も増えます。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
※注:引用箇所冒頭の「体感」とは、オイシックス・ラ・大地の独自施策を指す。社員が農産物の生産者と一緒に畑を耕したり、顧客をオフィスに招いてパネルディスカッションを行ったりと、関係者との接点を増やすことで、社員のモチベーションを自発的に高める効果を見込んでいる。
※出典:コスモ教育出版の月刊誌『理念と経営』2023年8月号「巻頭対談・本気で会社を変えたければ、まず社長が自らを改革せよ」
そういう社員がいたとしても、基本的には何もしません。というのも、オイシックスのマネジメントの基本方針は「動機づけできない社員に時間とエネルギーを費やすより、エースを超エースにすることに費やせ」だからです。そのほうが組織の勝率は上がるので……。
名和 「2:6:2の法則」というものがありますね。あらゆる組織で、上位2割が成績優秀者、6割は平凡、残り2割が成績不振者に分かれるというものです。普通のマネジメントは、「上の2割は自走できるから放っておこう。自走できない下の2割を伸ばそう」としがちです。でも、御社は逆なんですね。
高島 はい。下の2割を底上げしても、組織全体としてはあまりハッピーにならないですから。それより、上位2割がさらに頑張って道を切り拓いてくれたほうが、結果的に下の2割が活躍する場も増えます。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
※注:引用箇所冒頭の「体感」とは、オイシックス・ラ・大地の独自施策を指す。社員が農産物の生産者と一緒に畑を耕したり、顧客をオフィスに招いてパネルディスカッションを行ったりと、関係者との接点を増やすことで、社員のモチベーションを自発的に高める効果を見込んでいる。
※出典:コスモ教育出版の月刊誌『理念と経営』2023年8月号「巻頭対談・本気で会社を変えたければ、まず社長が自らを改革せよ」
いかがだろうか。このようなリーダーシップは、チームとしてのパフォーマンス向上に長けた日本人経営者であれば、身につけやすいのではないだろうか。
ただ、そのためには「勝つ」ことへの執念が、異常なほど強くなければならない。そしてそれは独り勝ちではなく、組織全体、さらには周りを巻き込み、みんなで勝利して成長していくことが目指されなければならない。