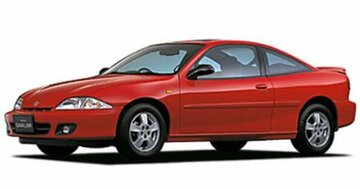わが国サイドが犯した「重大な失敗」とは
わが国は、米国政府の機能低下に付き合ってしまった格好だ。7月22日の交渉を控えて、赤沢氏はラトニック商務長官の私邸にまで呼ばれ、トランプ氏が重視する事項を詰めた。そこまでは良かったのだが、合意文書を作らずラトニック氏との口約束で終わった。これは、わが国の失態と非難されても仕方がないだろう。
相手の事情がどうであれ、合意した内容は文書に落とし込み、両国首脳のサインを取って公表すべきだった。口約束した内容がひっくり返されるリスクを防ぐためだ。特に、現在の米国政府の機能低下を考えると、口約束だけで十分とはいえない。
どうしてここまで言うかというと、欧州委員会は、それなりにきちんと対応していたからだ。日本との違いは、文書を確認すると明らかだ。
7月23日にホワイトハウスが発表した対日交渉の概要書(ファクトシート)の主な内容は、わが国から米国へ投資を増やすことについてだった。関税=Tariffは3回しか登場しない。相互関税、自動車関税を15%にすること、半導体や医薬品に関する記述はなかった。
日本側は25日、『米国の関税措置に関する日米協議:日米間の合意(概要)』を発表した。この冒頭では、「相互関税と自動車関税が15%になる」と記載されている。米国が、既存関税率15%以上の品目に追加関税を課さない「軽減措置」の記載もある。半導体・医薬品など分野別の関税で米国は「日本を他国に劣後する形で扱わない」との記載すらある。ところが、いずれも米国のファクトシートに記載はない。
一方、28日にホワイトハウスは欧州委員会とのファクトシートを発表。29日に欧州委員会も『EU-US trade deal explained』を公表している。それぞれ読むと、米-EU間でも相互関税率ゼロ品目の設定を巡って食い違いは残ったが、自動車を筆頭にした重要項目の関税は記載してある。
欧州委員会は、事前に米国の政府機能の低下や一部の行政混乱を理解し、事前に合意文書の大枠を米国と調整した可能性が高い。いずれにしても、結果を比較すれば日本の重大な失敗が浮き彫りになっている。
ただし、欧州委員会がそこまでしても、トランプ氏の意向で関税が再度引き上げられる可能性は残る。それほどトランプ氏独断のリスクは大きいのだ。