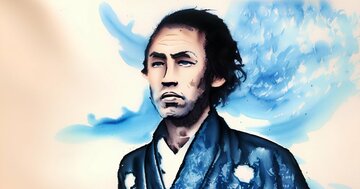「私もやってた…」となりたくなければ知るべき、危険な飲み方ワースト1
「仕事が遅い部下がいてイライラする」「不本意な異動を命じられた」「かつての部下が上司になってしまった」――経営者、管理職、チームリーダー、アルバイトのバイトリーダーまで、組織を動かす立場の人間は、悩みが尽きない……。そんなときこそ頭がいい人は、「歴史」に解決策を求める。【人】【モノ】【お金】【情報】【目標】【健康】とテーマ別で、歴史上の人物の言葉をベースに、わかりやすく現代ビジネスの諸問題を解決する話題の書『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、伊達政宗、島津斉彬など、歴史上の人物26人の「成功と失敗の本質」を説く。「基本ストイックだが、酒だけはやめられなかった……」(上杉謙信)といったリアルな人間性にも迫りつつ、マネジメントに絶対活きる「歴史の教訓」を学ぶ。待望の続編『リーダーは世界史に学べ』(ダイヤモンド社)では、世界史のリーダー35人が、迷える現代のリーダーに【決断力】【洞察力】【育成力】【人間力】【健康力】という5つの力を高めるヒントを伝授する。
※本稿は『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
ビジネスの潤滑油、その光と影
酒を交えてのコミュニケーションは、日ごろは話せないことでも腹を割って話せることもあり、ビジネスで欠かせないものといっても過言ではありません。
ひと昔前のマスコミ関係の酒を交えたコミュニケーションは、たいへん盛んだった印象があります。
知り合いの大手広告代理店の社員から聞くところによると、公私ともに長年にわたる飲酒が災いしてか、退職後に体調を崩してしまう先輩が多いそうです。
まずは「己が器」を知ることから
功罪両面をあわせもつ酒と上手につき合うためには、毛利元就同様にアルコールに対する自分の耐性を知ることが前提です。
国が初めて示した「飲酒の羅針盤」
飲酒にともなうリスクを周知して、アルコールによる健康障害を防ぐため、厚生労働省の検討会は2024年、年齢や体質に応じた留意点などを盛り込んだガイドラインをまとめました。
飲酒についての指針を国が策定するのは初めてのことですが、飲むときには事前に食事をとったり、休肝日を設けたりするなど体に配慮するようすすめています。
健康の鍵は「純アルコール量」にあり
酒を飲むと顔が赤くなるアルコール分解酵素の働きが弱い人は、口内や食道にがんが発症するリスクがとても高くなるという報告があるとして、「純アルコール量(g)」に注目することが重要としています。
計算方法は次の通りです。
ここが分かれ道…リスクを高める飲酒量
生活習慣病リスクを高める飲酒量は、政府の健康づくり計画「健康日本21」(第3次)にある1日あたりの純アルコール量「男性40g以上、女性20g以上」としています。
純アルコール量20gは、日本酒1合、ビール中瓶1本に相当します。
その一杯が命取りに?避けるべき危険な飲み方
避けたい飲み方としては、一度の飲酒で純アルコール量60g以上を摂取したり、不安や不眠を解消するために飲んだり、他人に飲酒を強要したりすることを挙げています。
健康に配慮するためには、あらかじめ酒量を決めておくことも有効だとしています。