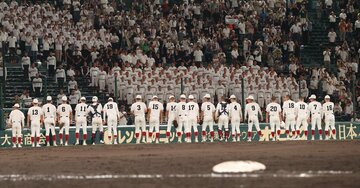この文脈における「空気」と言えば、評論家の山本七平が1977年に発表し、日本人論のスタンダードとして定着した名著『「空気」の研究』が真っ先に思い浮かぶ。日本の社会を支配しているのは厳格なルールや論理性・合理性ではなくその場の空気であり、組織の意思決定においてすら空気が優先される。世論に左右されやすい政治、熱しやすく冷めやすい国民性、ムラ社会の因習、学級会による特定生徒のつるし上げ、「言わずもがな」や「空気を読む」ことが善しとされる日本人的気質。すべて「空気」の産物だ。
『シミュレーション〜』を見ていて、ふと気づいたことがある。当時の空気支配の解像度をもう少し上げていくと、部員による暴力行為によって甲子園を2回戦で辞退した広陵高校の周辺で起こっていることを、どこか連想させるのだ。
過剰な現場尊重主義
日本では長らく、高校球児の厳しい上下関係や過酷な練習に関してマスコミが批判的な報道をすると、元甲子園球児から「経験したことがないくせに、わかったようなことを言うな」といったクレームが一定数寄せられる。今回の広陵高校の報道に対しても「強豪校の現実とはそういうもの。それを耐え抜いた者が一流のプロになれるのだ」と諭すようなポストがXでも散見された。
この現場尊重主義と呼ぶべきものは、太平洋戦争中にも発生している。大本営発表だ。
大本営は日本軍の最高統帥機関で、そこが行った戦況の公式発表を大本営発表と呼ぶ。太平洋戦争末期には戦況が劣勢であるにもかかわらず、さも優勢かのような情報を流し、各新聞はそのまま報じた。
なぜ大本営は真実を発表しなかったのか。その理由のひとつが、大本営が現地部隊からの報告をそのまま発表していたことだ。
辻田真佐憲・著『大本営発表 改竄・隠蔽・捏造の太平洋戦争』によれば、「どんなに熟練のパイロットでも、艦種を誤認したり、希望的な観測で戦果を判断してしまう傾向があった」という。それに加えて、部隊から報告されてきた戦果を大本営報道部がさらに査定するようなことは許されない「空気」もあった。前線で命を賭けて戦っている者たちの言うことを疑うなど何事か、というわけだ。
空調の効いた部屋にいる偉いさんではなく現場で汗をかいているやつの言うことを信じる、という判官びいき的な考え方が、昔も今も日本人は大好きだ。『踊る大捜査線』の「事件は会議室ではなく、現場で起きている」そのものである。