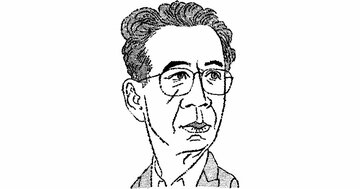稀代のメディア王・菊池寛が成功の裏で捨てたものの哀しさ
文芸作品を読むのが苦手でも大丈夫……眠れなくなるほど面白い文豪42人の生き様。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、名前は知っていても、実は作品を読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文芸作品が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。ヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を大公開!
※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。
 イラスト:塩井浩平
イラスト:塩井浩平
大ヒット作『真珠夫人』作者
マルチな才能に驚愕
月給25円の新聞記者、文壇への第一歩
かなりの紆余曲折を経た菊池寛は、大正5(1916)年に京大を卒業後、昭和11(1936)年に廃刊するまで東京五大新聞(東京日日新聞、報知新聞、時事新報、國民新聞、東京朝日新聞)の1つに数えられた『時事新報』の社会部記者となり、月給25円のうち10円を毎月実家に送金していたといいます。
入社の翌年(大正6〈1917〉年)、資産家である高松藩旧藩士・奥村家一族の奥村包子(かねこ)と結婚。これは、生活のための“戦略結婚”ともいわれます。
お金の心配がなくなったこともあってか、このころから菊池は執筆活動に軸足を置き始めます。そして大正8(1919)年、雑誌『中央公論』に短編小説『恩讐の彼方に』を寄稿したのを機に時事新報を退社して、執筆活動に専念することにしました。
ベストセラー作家誕生、そして新たな舞台へ
すると、その翌年(大正9〈1920〉年)、大阪毎日新聞・東京毎日新聞に連載した大衆小説『真珠夫人』が話題を呼び、一気に人気作家の仲間入りをしたのです。
このころになると日本の識字率は向上し、新聞や雑誌、小説を一部のブルジョワジーだけでなく一般大衆が読んだり買ったりする風潮ができてきました。
芥川龍之介など、名だたる作家たちと親しくしていたこともあり、タイミングを読むのもうまかったのでしょう。大正12(1923)年、菊池が35歳のときに、若手の作家たちに活躍する場を与えようと雑誌『文藝春秋』を立ち上げたのです。
驚異の創刊号、時代を掴んだヒット戦略
菊池が立ち上げた『文藝春秋』創刊号は、発行した3000部がわずか3日で売り切れになるほどのヒットを記録。2号目からは、すでに小説家として名を馳せていた自身のネームバリューを利用して、表紙に「菊池寛編集」という文字を大きく入れました。
この狙いが的中して、販売部数をさらに伸ばします。また、創刊と同じ年に発生した関東大震災の復興支援の空気が醸成されていたこともあって、『文藝春秋』は部数を重ねるごとに人気を博していきました。
震災復興の波に乗り、稀代のメディア王へ
関東大震災といえば、「鎌倉文士に浦和画家」といわれます。これは関東大震災で壊滅状態になった東京から鎌倉へと移り住んだ文学者と、埼玉・浦和へと移り住みアトリエを構えた画家が多かったことに由来します。
それほど大きなダメージから復興需要が生じた影響が、文化・文芸にも浸透してくるようになったのです。昭和初期に起こった1冊1円の「円本ブーム」に加え、外国作家の翻訳本なども、ものすごい勢いで売れるようになりました。
首都・東京の災害復興によって、広く日本全体の文化力を底上げするムードが満ちていました。そういう状況下にあって、菊池は『文藝春秋』をただの文芸誌ではなく、世の中の「流行」や「ゴシップ」など扱うネタの間口を広げていったのです。
こうして、小説家、新聞記者、プロデューサー、編集者、「文藝春秋」の経営者と、菊池の肩書きは次々に増えていきます。