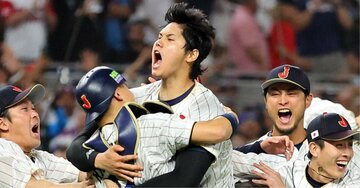こんな広告を目にしたら世論的には「ネットフリックスは馬鹿正直な会社だ」という良い評判が立つでしょう。そこで決勝戦あたりには、「明日の新聞でネットフリックスの解約の仕方を読んでくださいね」と呼びかけます。
決勝翌日の3月13日、全国5紙の見開き全面広告では、WBCへの感謝とともにネットフリックスを解約するやり方の説明が書かれた広告を出稿するのです。その広告の中で、たとえば綾瀬はるかさんに、「でもあと一カ月、続けてくれたら嬉しいな」とアピールしてもらったらどうでしょう。
日本の60代、70代はバブル世代です。こうやってくすぐることで逆にネットフリックスを継続してくれる人が400万人は出てきそうです。まあネットフリックスの幹部は鉄人ぞろいですから、実際はこれよりももっといい戦略を打ち出してくるでしょう。お手並み拝見です。
さて、2026年のWBCはそれで視聴者もネットフリックスも双方満足だとして、その後、わたしたちにはどんなことが起きるのでしょうか?
確実に予測されることは放映権の高騰がこれから先も続くことです。そして問題になるのはいつかの段階で、高額のスポーツイベントの放映権料を新規顧客獲得のマーケティング費用で回収できなくなる時期が訪れることです。
2022年のW杯のABEMAにしても、今回のネットフリックスにしても、新規顧客の数を増やすという狙いに合致するからこそ100億円規模の投資をしたうえで無料開放でもペイするのです。前提としてテレビから視聴者を奪えたからこそこの投資が成立しました。
一方で井上尚弥の独占配信でAmazonが無料配信しなかったのは、すでにAmazonプライム会員数が十分に大きいため、無料開放で追加の会員を増やす効果が限られるせいでしょう。井上尚弥の放映権の獲得は、既存会員にプライムビデオの存在を周知する狙いの方が重要だったのだと推察されます。
そして未来のどこかの段階で、テレビが衰退した結果、有力コンテンツは動画配信ばかりが見られる時代になったらどうでしょうか?新規顧客獲得の余地がなくなった未来では、高騰したスポーツイベントの視聴を無料で賄うことは不可能になります。
その時代、最終的には3の「オンデマンド課金」の方式に世の中は収れんしていきます。オリンピック、W杯、F1、メジャーリーグといった世界的なスポーツイベントは一回2000円を払って視聴するのが常識だという未来が最後の最後にやってくるのです。