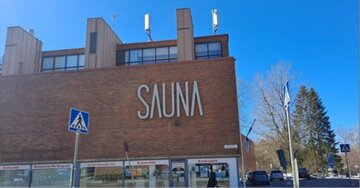「シス」を有名にした
第二次世界大戦の出来事
例えば、「フィンランドのアイスホッケーの選手たちは諦めずにシスを発揮して一番のライバル(そしてとても仲のいい)スウェーデンに勝った」というニュースや、「手術の後のリハビリはシスが必要だ」という記事、さらには「最近の若い人はシスが足りない」という年配の方のご意見などから見つけられることもあります。
また、交通機関のストライキで通勤できない時に、大雪の中クロスカントリースキーで会社に行った人のシスをほめたたえる声掛けも見受けられます。シスの形容詞は「sisukas(シスカス)」、例えば「Oletpa sisukas!=あなたはシスを持っているね!」といったように使います。
シスは自分に対しては使わないのですが、誰かに「sisukas」と言われたら、一番のほめ言葉です。
シスは、日本人も共感しやすいフィンランドの国民性のようで、日本でのテレビ出演やトークイベントに登壇する時には「ぜひ紹介してほしい」、とお声がけいただくことが多かったのですが、今までシスについて話すのは少しとまどいがありました。
というのも、シスがあるからフィンランドは幸せ、という結びになってしまうのはとても単純すぎるし、かといって、ヒュッゲフィーカのような豊かな暮らしに結び付くものでもない別世界の言葉だからです。
シスという言葉が世界的に有名になったのは、フィンランドでは冬戦争と継続戦争と呼ばれる1939年以降の第二次世界大戦の時。旧ソ連によるフィンランドへの侵攻の際、小国フィンランドが巨大なソ連に立ち向かいシスを発揮して独立を失わなかったという歴史があるため、簡単には触れられないことだと思っていました。
 同書より 拡大画像表示
同書より 拡大画像表示
フィンランド人がシスを培ってきた理由、そして幸せを感じられる理由は共通の背景があると信じています。フィンランドの幸せとは、もしかしたら今のままで十分満足している、大丈夫、という満ち足りた幸せなのかもしれません。それには、フィンランドの時には厳しく、時には美しい自然環境も影響しています。