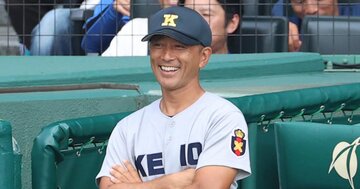でも、一〇代から「女性が身の回りのケアをして当たり前」の環境で過ごした男性が社会に出て、その過去をきっぱり忘れ去り、女性と対等に向き合うことができるのだろうかと、「感動をありがとう」といった球児への感謝のツイートの群れを見ながら考え込んでしまいました。
野球だけでなく、あらゆる体育会系の部活動において、マチズモ(引用者注:男性優位主義的な考え方のこと)の源泉、マチズモの原体験が潜んでいるのでは……と想像するのですが、いかがでしょうか?
すべての高校生が、否、すべての人が、誰かに「連れて行って」もらうのではなく、自分の意志で、自分の力で、行きたい場所にどこにだって行けるような環境で生きられたらいいのにと切に思います。
野球だけでなく、あらゆる体育会系の部活動において、マチズモ(引用者注:男性優位主義的な考え方のこと)の源泉、マチズモの原体験が潜んでいるのでは……と想像するのですが、いかがでしょうか?
すべての高校生が、否、すべての人が、誰かに「連れて行って」もらうのではなく、自分の意志で、自分の力で、行きたい場所にどこにだって行けるような環境で生きられたらいいのにと切に思います。
『タッチ』の浅倉南は
野球に何を求めていた?
これを受け、武田は大ヒットした野球漫画『タッチ』(あだち充作、『週刊少年サンデー』で1981~86年まで連載)を引き合いに出し、さらなる批判を展開する。
『タッチ』は発行部数1億部を超える野球漫画としては最大のヒット作で、双子の兄弟である上杉達也、和也、そして幼馴染の浅倉南の3人を中心に高校野球と青春が描かれた漫画だ。なかでも南の「甲子園つれてって」というセリフはよく知られており、高校野球の女子マネージャーの典型的キャラクターであると一般に思われている(実際はだいぶ違うのだが、長くなるのでここではあまり深入りしない)。
武田は、先の『女子マネージャーの誕生とメディア』を引用しつつ、次のように述べる。
高井昌吏は、試合終了後に円くなって涙する部員が、監督に促されて女子マネージャーを慰労する拍手を送っていた例や、卒業時にユニフォームをプレゼントされて感動した女子マネージャーの例などをあげながら、女子マネージャーは戦う集団の中にいるのではなく、彼らとともに泣いているのでもなく、「男たちの感謝の気持ちによって心を打たれ、その結果涙し、感動している」(傍点原文)のであり、それは代替満足なのだとした。
(中略)
確かに浅倉南が欲していたのは、まさに「代替満足」そのものだった。(中略)「代替」の濃淡によって感動のボルテージが定まる。その調整弁を握るのは女子ではない。絶対に男子なのだ。
(中略)
確かに浅倉南が欲していたのは、まさに「代替満足」そのものだった。(中略)「代替」の濃淡によって感動のボルテージが定まる。その調整弁を握るのは女子ではない。絶対に男子なのだ。