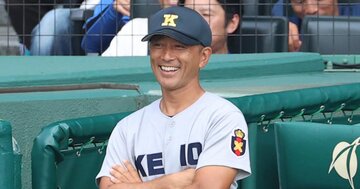女子マネージャーの自意識に
過剰に着目することの“落とし穴”
ここから武田は、2014年夏の甲子園で起きた「おにぎりマネージャー事件」に触れる。春日部共栄の女子マネージャーが部員のためにこれまで通算2万個のおにぎりを握ったことが美談として報道され、逆にSNSユーザーたちからは「いまだに性別役割分業を肯定している」「それを美談にするメディアも時代遅れだ」と激しく批判された事件である。武田は次のように論を進める。
「代替満足」を得る方法を自分で選び抜く、というスッキリしない主体性に、外から何かを言うことはできるのだろうか。補助的業務に従事するという彼女の判断を否定することはできないし、その必要もない。そのポジションにおさまることを咎めるのではなく、そのポジションが微動だにせず「女性が身の回りのケアをして当たり前」になっていることに違和感を持ちたい。
高井や武田らは、女子マネージャー個々人を批判することを周到に回避しながら、その自意識(自分が周囲からどう見られているかを気にする意識)のあり方を問題視する。ここで中心的な問題とされているのは、女子マネージャーのアイデンティティなのである。
『負け犬の遠吠え』などで知られるエッセイストの酒井順子も、著書『男尊女子』(集英社、2017年)のなかで、女子校の同級生たちが大学に入って嬉々として運動部の女子マネージャーになっていく現象を、やはり彼女たちの自意識に着目して面白おかしく描いている。
マネージャーの自意識に着目するこのような問題化の仕方は、文化人たちの「手癖」でもあるようだ。ここで私がさしあたって指摘しておきたいのは、自意識に過剰に着目することで、かえって現実に起きている問題の本質が見えづらくなっているのではないか、ということである。
一般に、野球は体育会系の権化であり、体育会系は個人主義的ではなく集団主義的な文化だと理解されている。それを象徴するのが、2010年代後半に高校演劇界を席巻した『アルプススタンドのはしの方』という戯曲である。