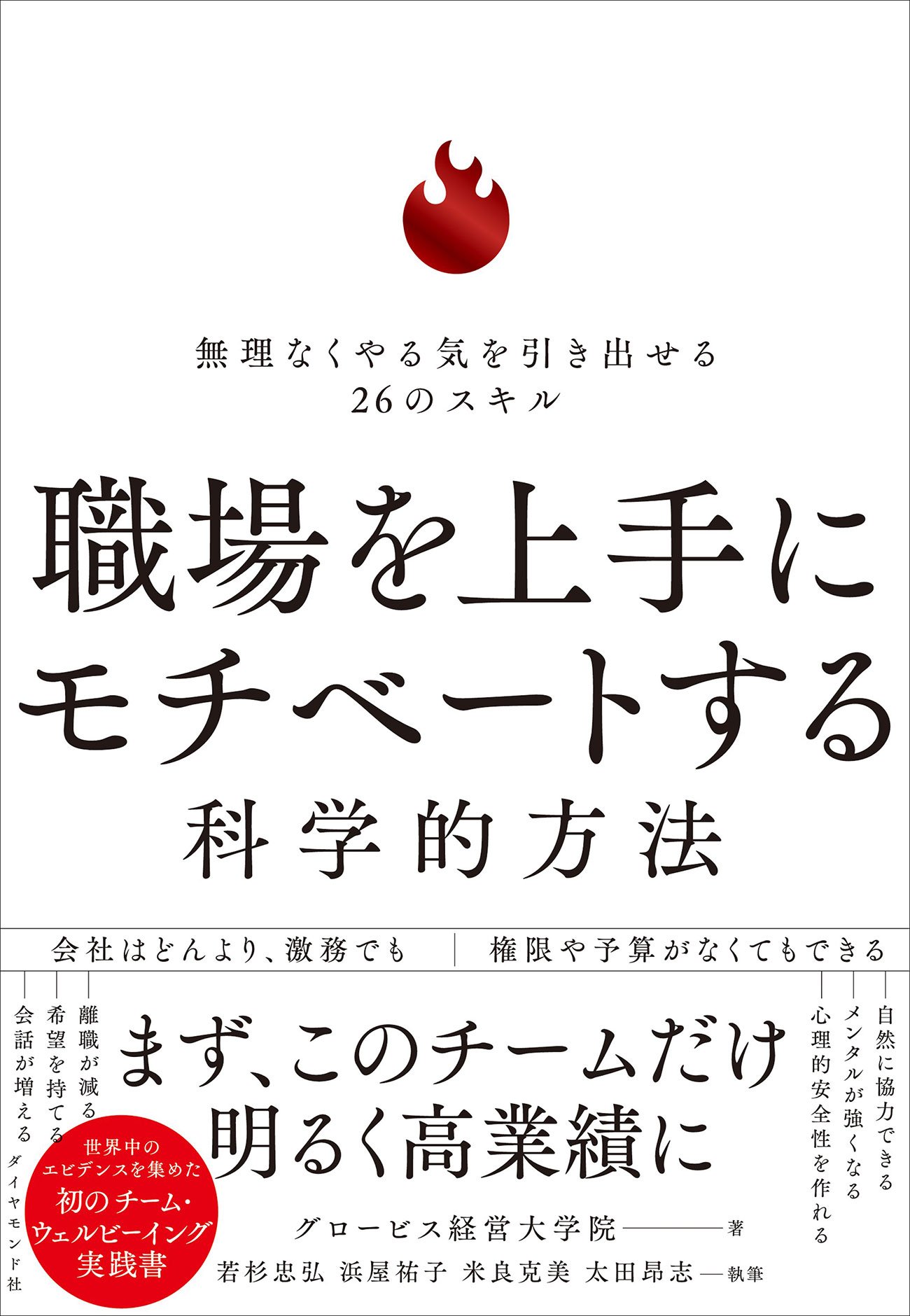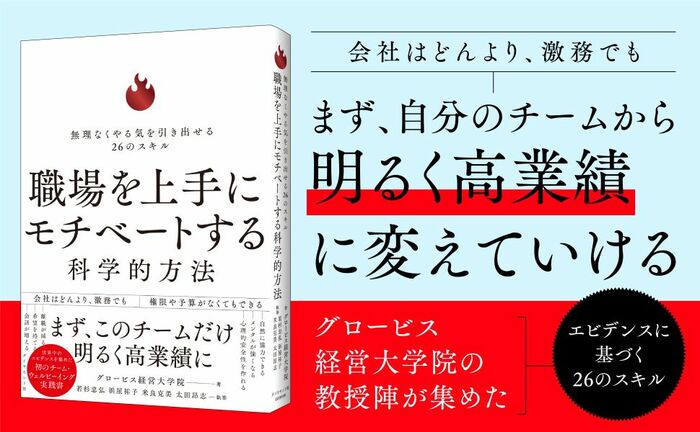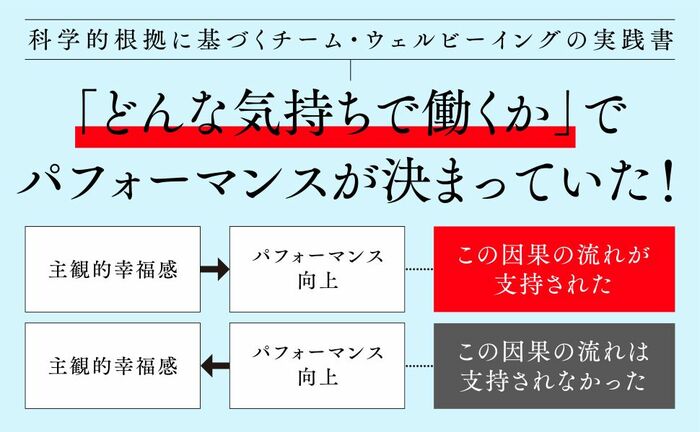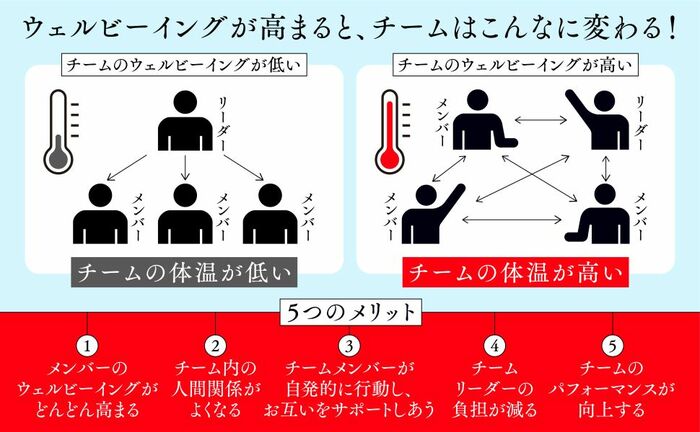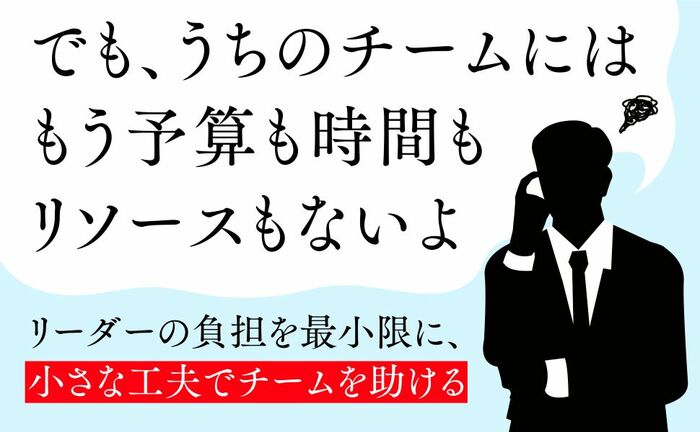裁量を重視した仕事の配分を考える
まず、仕事の裁量とは何なのかを考えてみましょう。仕事の裁量とは、「その仕事をどのように進めるかを自分で決められること」を指します。厚生労働省が推奨するストレス調査では、仕事の裁量度を次の項目で判断しています[2]。
(1)自分のペースで仕事ができる
(2)自分で仕事の順番・やり方を決めることができる
(3)職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる
「ほどよいストレス」は仕事の負荷と裁量で決まる
仕事の裁量の大小がウェルビーイングにどのように影響するかを理解するうえで役立つのが、スウェーデンの心理学者、カラセックが提唱した「仕事の要求度-コントロールモデル(JD-Cモデル)」です[3]。仕事の要求度とは、仕事の量や時間や責任などを指します(以降では理解を容易にするため、まとめて「仕事の負荷」と呼びます)。また、仕事のコントロールとは、仕事の進め方の裁量を指します。
つまり、このモデルは、「どのくらいの重さの仕事をするか(仕事の負荷)」と「その仕事をどう進めるかを自ら決められるか(裁量)」の関係性を示しているのです(図3-2を参照)。
両者の組み合わせのなかで心身の不調につながるリスクがもっとも高いのが、「仕事の負荷が大きく、裁量が小さい状態」(図の右下)です。自分が「質量ともに重たい仕事をやらねばならないが、自分で進め方を決める余地は少ない」状態に置かれていることを想像すると、これが大きなストレスを生む状態であることが容易にわかるでしょう。
また、「仕事の負荷は小さい、もしくは適正であっても、どのように進めるか自分で決める自由がない状態」(図の左下)の場合、メンバーは受け身でただ仕事を「こなす」ようになりがちです。このような状態が続くとワーク・エンゲージメントに悪い影響が出ることが予想されます。冒頭の小野さんのチームのメンバーは、この状態に陥っていないかチェックする必要があるでしょう。
チームメンバーへの仕事の渡し方は、「負荷が小さければよい」「裁量が大きければよい」といった単純なものではありません。仕事の負荷と裁量の両方に目配せして、メンバーの活性化につながる「ほどよいストレス」を心がけたいものです。
チームメンバーの仕事の裁量度合いをチェックしてみよう
小野さんのように、メンバーに仕事を任せるにあたって、経験や力量を踏まえてちょうどよい重さの仕事を渡すように配慮しているというリーダーは多いでしょう。
しかし、適度な裁量を与えることについては、見落としがちではないでしょうか。メンバーが自律的に仕事を進められるような裁量を渡せているか、チームメンバーの顔を思い浮かべつつ、次のチェックリストを用いて振り返ってみましょう[4]。
チェックリスト
(1)自分のペースで仕事ができる
□要所ごとの確認は行うものの、細部についてはメンバーが自分でペース配分できますか?
□休憩を取るタイミングをある程度柔軟に決められますか?
(2)自分で仕事の順番・やり方を決められる
□どこまではメンバー自身の判断で進めていいと、あらかじめ伝えていますか?
□目的を達成するための手段を細かに定めすぎて、アイデアを発揮する余地を奪ってはいませんか?
□頻繁に発生する業務について、必要がないのにそのつど上位者に指示を仰ぐプロセスにしていませんか?
(3)職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる
□仕事の方針が決まってから一方的に命じるだけになっていませんか?
□仕事の担当や計画を決める場にメンバーは参加していますか?
国内外での調査では、男性、管理職、専門・技術職、大卒・大学院修了、正社員という属性をもつことが、仕事の裁量の大きさにつながる傾向が明らかになっています[5]。
ただし、それ以外の職種や属性であっても、仕事の裁量を増やすことは日常のちょっとした場面から可能です。
たとえば、裁量の少ない仕事のひとつであるデータ入力事務においても、目標や締め切りの設定をメンバーに主導してもらう、それに応じてペース配分をメンバーに任せる、量だけでなく質の向上の取り組みを奨励する、といった工夫が考えられるでしょう。
みなさんのチーム内の仕事についてもこのチェックリストを使って、メンバーの自律性を高める仕事の渡し方について、工夫できる余地はないか考えてみましょう。
裁量を与えるのが適さないケースもある
多くの場合、仕事の裁量を与えて自律性を高めることは、メンバーのストレスを和らげ、ウェルビーイングを向上させます。
しかし、常にそうだとはかぎりません。メンバーの状態や置かれた状況によっては、仕事の裁量が大きいことが混乱やストレスの増大を引き起こすケースもあることには注意が必要です。
たとえば、仕事の裁量が大きければ一定以上の自己管理能力が求められますが、自己管理が苦手なメンバーの場合には、自己裁量が大きくなることで逆にストレスが増えるおそれがあります。
また、仕事の裁量が大きいものの必要なサポートが不足している場合にも、負荷が増えてストレスが増すことがあります。
仕事の裁量を与えることは、メンバーのモチベーションやパフォーマンスの向上、離職率の低下などの効果があることが報告されていますが、けっして万能のツールではありません。
高ストレスや混乱を招くことは、もちろん本意ではないはずです。メンバーがそれぞれの持ち場でイキイキと働くことにつながるものであるかを、メンバー個々人に目を向けて判断していきましょう。
*この記事は、『職場を上手にモチベートする科学的方法――無理なくやる気を引き出せる26のスキル』(ダイヤモンド社刊)を再編集したものです。
[2] 厚生労働省『職業性ストレス簡易調査票(80 項目版)』
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/pdf/stress-check_80_j.pdf
[3] Karasek Jr, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. Administrative science quarterly, 285-308.
[4] 2をもとに筆者作成。
[5] Lopes, H., Calapez, T., & Lopes, D. (2017). The determinants of work autonomy and employee involvement: A multilevel analysis. Economic and Industrial Democracy, 38(3), 448-472.