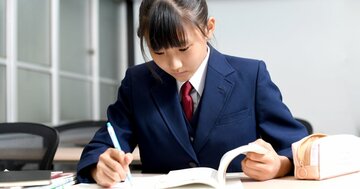上位校のほうが教育の特色が薄いという側面も
意外かもしれませんが、上位校のほうが教育の特色があまり感じられないということは往々にしてあります。
麻布や武蔵のような伝統校は「自由」という特色がありますが、それは学校が意図的に作った特色というよりも、結果的にそうなっているだけともいえます。もう一歩踏み込んだ時に何があるかという点では、教師個人の個性に依存していることが多く、学校としてのまとまった色を見つけづらいのです。
上位校の生徒は元々優秀で、「放っておいても伸びる」ため、先生たちは子供の個性を認めた上で、自由や個性を認めています。それが「勝手にしなさい、好きにしなさい」というスタンスに見えることが多いのです。
例えば開成の運動会は中高合わせて2100人規模ですが、生徒の自主性に任せています。個々の生徒の能力に任せられるからこそ、「自由」が体現されているという面もあるのです。
一方で、聖光、海城、豊島岡、洗足のような上位校の中で、かつての中堅校から成長してきた学校は、特徴的な指導方針を強く打ち出しているところが多く見受けられます。これらの学校には「これから歴史をつくっていく」という気概が強く感じられます。生徒たちにも折に触れ、「あなたたちはすごい」と、その学校の生徒であることのプライドと誇りを持つように日頃から教え込み、生徒の自尊心を守り育てています。
これらの学校は、80年、100年の歴史を持つ伝統校に追いつけ、追い越せという意志を持ち、「色」を作って一丸となって進んできており、それが学校全体のまとまりを生んでいます。この「勢い」が学校の特色となり、子どもたちの成長を促す力にもなっているのです。
ところで、「ワンランク落として中堅校に行く」という選択もよく耳にしますが、偏差値が5ポイント程度の違いであれば、「落とした」と言っても実質的に大きな違いはありません。
また、「落とした」からといって、その学校で一番になれるわけではありません。それでも、お子さんの性格や学習スタイルに合った環境を選ぶことで、6年間の中高生活を充実させることができます。上位校、中堅校という枠組みよりも、お子さんと学校の相性を重視した選択が重要なのです。