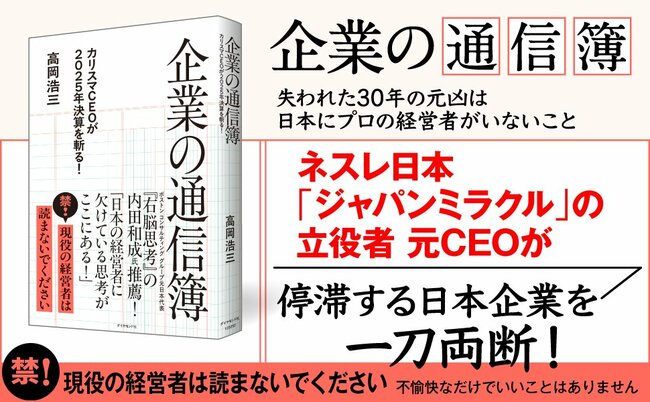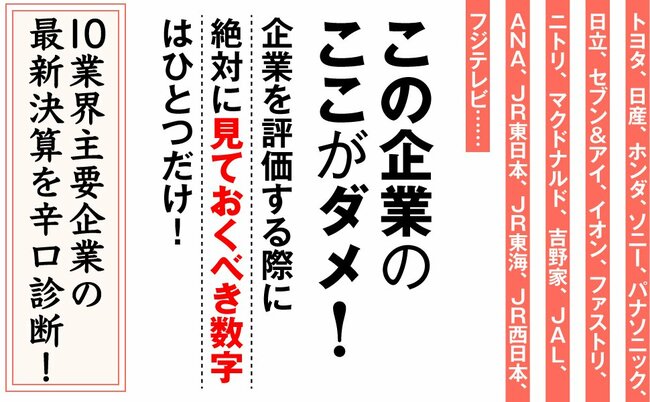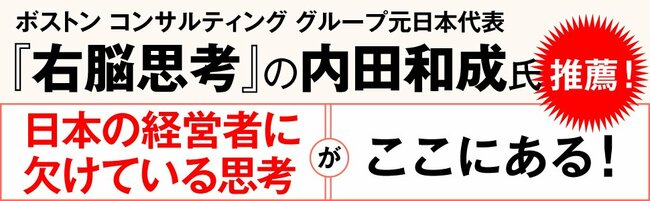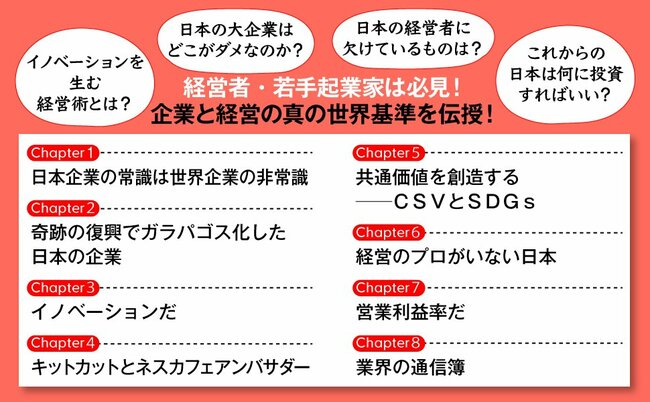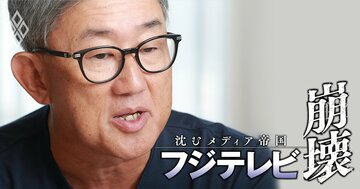日産の深刻な経営危機を招いたのは経営陣
責任うやむやのまま経営統合は言語道断
日産は9000人の従業員のクビを切らなければならないほどの深刻な経営危機に陥っていました。危機を招いたのは従業員ではなく経営陣です。
危機を乗り切るためにホンダと経営統合するというのなら、まずは経営陣全員が責任を取って辞任し、経営・執行陣を刷新して、新しい経営陣がそれを判断するのが筋です。現経営陣が経営危機を招いた責任をうやむやにしたまま、ホンダとの経営統合に活路を求めるなど言語道断です。子供でも分かる理屈です。
ですから、ニュースを聞いたときには本当に驚きました。経営陣が経営責任も取らずにホンダと一緒になるやなんて、そんなアホなことがあるんかいな、です。順序がまったく逆です。
ホンダの立場からすると、経営統合の前提には、日産が経営陣を刷新して、旧経営陣が公表したリストラ策よりも大きな再建策を示すことがあったのだと思います。
当然のことです。でなければ共倒れになる危険性があります。ところが、日産は経営陣を刷新するどころか、経営再建策すらまとめられませんでした。ホンダが日産が首を縦に振るはずのない子会社化を打診したのは、日産の意思決定の遅さに痺れを切らして、破談になってもよいと考えてのことだったのだと想像します。
巨額赤字、主力工場閉鎖、2万人削減…
日産の経営陣にはガバナンスがない
つまり、日産の経営陣にはガバナンスがないということです。取締役にはルノー出身の外国人社外取締役が2人入っていて多様性があるように見えますが、日産の大株主のルノーにしてみれば、お荷物になった日産は早く手放したいはずです。売るならできるだけ高く売りたいわけです。ホンダの子会社になれば二束三文で買いたたかれる可能性があります。
ですから、ルノー出身の外国人取締役も反対するわけです。利害関係が一致した仲良しこよしの取締役会です。それでは、株主利益を代表すべきガバナンスが機能するはずはありません。
ホンダとの経営統合が破談になった後も、内田社長は続投の意思を示していたそうですが、社内外からの経営責任を問う声にあらがう術もなく、退任に追い込まれました。そもそも、ホンダに助けてもらわなければならないほどの経営危機を招いたのですから、当たり前のことです。
2025年6月に開催された株主総会は、前日に内田社長に退職慰労金1億8700万円を含め総額3億9000万円の報酬を支払うことが開示されたこともあり、大荒れとなりました。これも当たり前です。が、内田社長からの謝罪はありませんでした。
2025年3月期の決算で日産は約6700億円もの巨額の最終赤字を計上。新社長となったメキシコ日産出身のイヴァン・エスピノーサ氏は、お膝元の主力工場である追浜工場の閉鎖を発表、人員削減規模は2万人にまで膨れ上がりました。
Key Visual by Kaoru Kurata