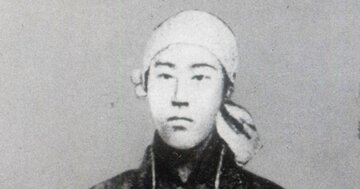生活環境への2次的な影響
臭気、騒音、振動
事故の直接的な被害だけでなく、その後の復旧作業や地盤の不安定化に伴い、周辺住民の生活環境にもさまざまな2次的影響が及びました。とくに事故後の数カ月で目立っていたのが、臭気、騒音、振動といった、日常生活の質に関わる変化でした。
現場周辺では、事故発生からしばらくして「下水のようなにおいが家の中まで入り込んでくる」「夜間に揺れを感じて眠れない」といった住民の声が寄せられるようになりました。復旧作業に伴う重機の稼働、土砂や汚水の処理などが、こうした現象の背景にあると考えられます。
そうした中、事故発生から約3カ月が経過し、ようやく仮設のバイパス管が完成しました。バイパス管は縦2メートル、横3メートル、長さ約20メートル。陥没現場と下水道管内に残された運転席部分を迂回させ、既設の下水道管に合流させます。
この措置により、破損箇所への下水の流入は大幅に減少し、ようやく現場の内部に立ち入る環境が整いました。
そしてこの環境の変化を受け、再び消防と警察による捜索活動が再開されました。5月2日午前、破損した下水道管内のトラック運転席付近から、男性の遺体が発見され、慎重に地上へ搬出されました。
しかし、仮設バイパスの完成はあくまで応急措置にすぎません。本格的な復旧に向けては、まず、破損した下水道管の仮復旧工事を行います。これは下水道管の内側に内径の小さな下水道管をつくるようなものです。その後、新たな下水道管を敷設する(複線化する)計画です。
含水率の高い地盤条件のもとで施工を進めるには、引き続き高度な水管理が欠かせません。
完全復旧まで
5~7年を要する理由
現場となった交差点にはいまなお巨大な陥没穴が残され、道路封鎖が続いています。現場は仮設フェンスで囲われ、周囲では依然として緊張感が漂っています。
埼玉県が設置した「復旧工法検討委員会」は、事故から2週間後の記者会見で「本格的な復旧には、急いでも3年程度はかかる」との見解を示しました。さらに、その後の調査や工法検討を踏まえ、すべての復旧作業が完了するまでには5~7年程度を要する可能性があるという見通しが公表されています。