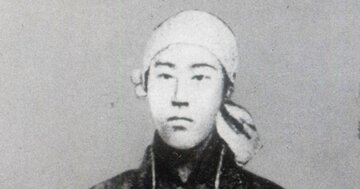土砂災害への対応としては、「トレンチレスキュー」と呼ばれる手法が有効とされています。これは、要救助者の周囲を板や鋼材などで囲い、土砂の崩落を防ぎながら、救助者と救助対象者双方の安全を確保する方法です。通常、崩落の危険性が高い現場では、こうした手法が採用されます。
あの情報があれば
初動対応は違っていた?
一方、現場の隊員にはトレンチレスキュー用の装備や訓練経験もありませんでした。装備や訓練がなければ、その手法を採用できなかったことは理解できます。
こうしてみると、今回の初動対応には、個々の判断を超えた組織的な備えの不足があったことがうかがえます。救助に必要な技術や装備が事前に準備されていなければ、現場の隊員は、最善を尽くそうとしても限られた手段の中で判断を下さざるを得ません。
いまから振り返ってみれば、もし事前に共有されていたら判断が変わったかもしれない情報がいくつかあります。
1つは、地質地盤の情報です。事故現場周辺の地盤は、主に砂やシルトといった比較的粒径の細かい土で構成されており、水分を含みやすく、沈下や圧縮が生じやすい軟弱地盤です。こうした地質の特性は、崩落のリスクや重機使用の可否を見極めるうえで重要な判断材料になるでしょう。
もう1つは、地下構造物の配置情報です。現場周辺には、破損した下水道管だけでなく、水道管、ガス管、電力ケーブル、通信ケーブルなど、多数のライフラインが埋設されています。これらの構造物が、どの位置にあるのか。図面や施工記録の有無、更新の正確性によって、安全な作業区域の設定や機材の選定にも大きな影響が出ます。
さらに、硫化水素の発生も、現場では障害の1つとなりました。下水道内では有毒ガスが発生することがあり、破損した管から漏れ出す硫化水素が救助活動の妨げになることもあります。ガスの有無や濃度、対策方法なども、事前に情報として把握されていれば、より柔軟な対応が取れた可能性があります。