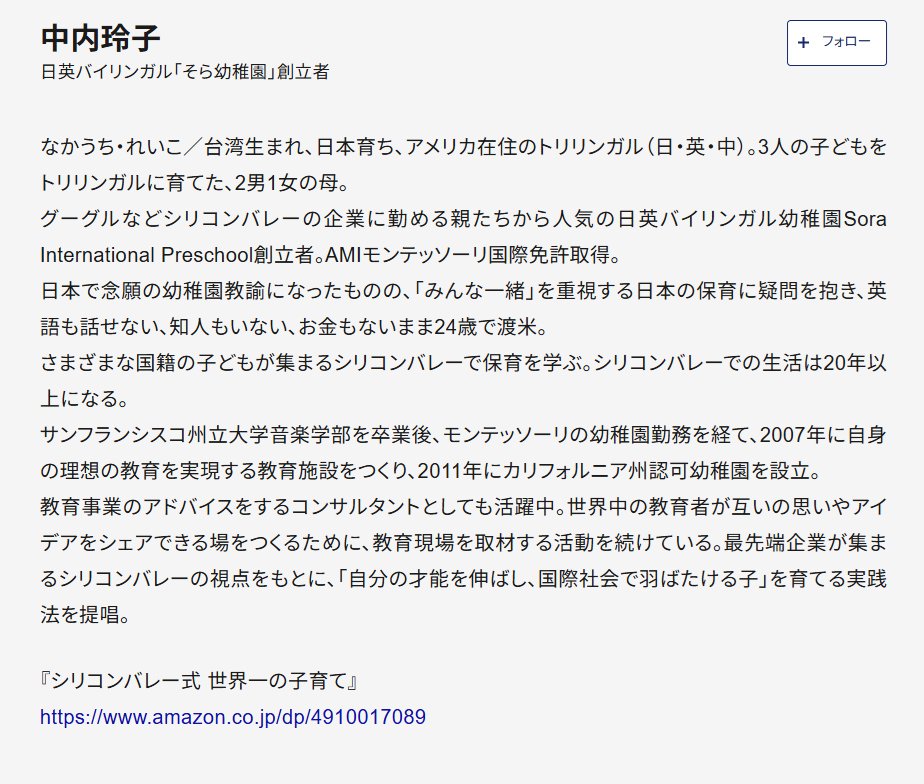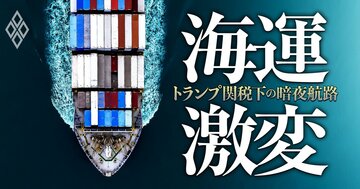グローバルマナーの本質は
シンプルな「思いやり」の物差し
自文化の「当たり前」は、異文化の中では必ずしも通用しません。それが時として、意図せず相手を不快にさせたり、逆に相手の言動を過剰に解釈してしまったりする原因にもなり得ます。
「多様性を尊重する」とは、あらゆる文化や価値観を無条件に許容することとは少し違うと、私は考えています。大切なのは、互いの文化に敬意を払いながらも、「この共有空間で、みんなが快適に過ごすためにはどうすべきか」を共に考える姿勢です。
自分の「権利」を主張する前に、自身の言動が周囲に与える「影響」を想像してみる。このバランス感覚こそが、グローバルな環境で求められる本質的なスキルだと、私は保育の現場を通して確信しています。
このキムチ事件を、「人種差別だ」と一言で片付けてしまうには、あまりに多くの感情が隠されています。「慣れない匂いが苦手」という素直な気持ちと、「大好きなものを否定された」という悲しい気持ち。どちらの心にも、きっと悪意はなかったはずです。
これは、遠いアメリカだけの話ではありません。日本人の地域社会においても、似たような認識の齟齬は、日々起こり得ることです。
もし、文化的な背景の違いからくる違和感や対立に直面した時、一度立ち止まって、このシンプルな物差しを当ててみてはいかがでしょうか。
「相手は、私を意図的に“不快”にさせようとしているのか?」
そのように一歩立ち止まることが、不必要な対立を避け、互いを理解し合うための建設的な対話へとつながるのではないでしょうか。