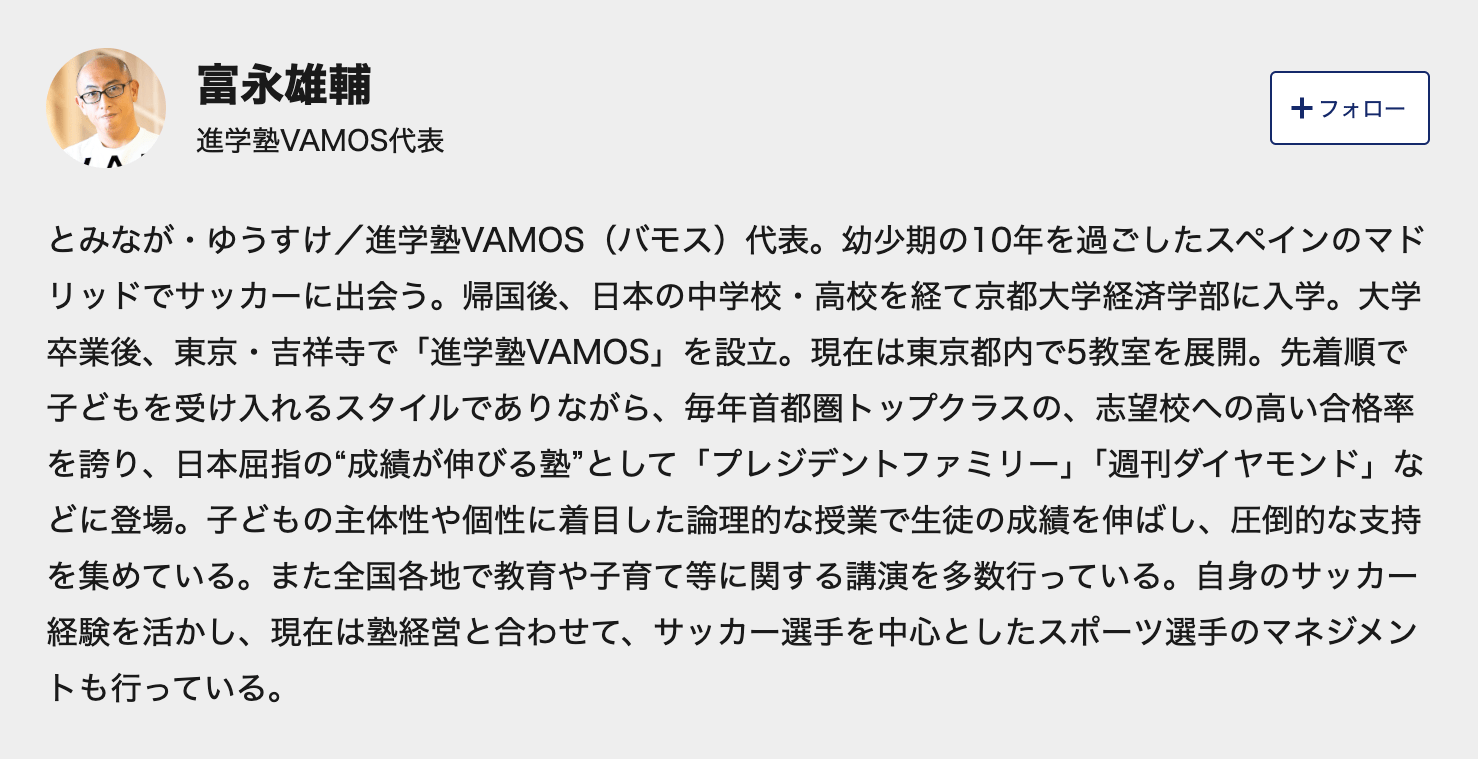勉強もスポーツも「得意の一点伸ばし」で総合力は高まる
得意なものを伸ばせば、最終的に総合力もつくということを述べてきました。これは、その科目がさらに得意になって、総合点が上がるという側面もありますが、実際にそれ以上に大きいのは、子どもに自己肯定感と自信がつくことです。
得意科目で、ちょっとやそっとのことでは崩れないような自信が持てれば、苦手科目の成績が悪いことも「平気」だと思えるようになり、勉強そのものが楽しくなります。勉強が嫌いではなく、自然に継続学習できている状態――それが外から見れば地頭のよさということにもなるでしょう。
前述したのはたまたま数学が突出してできる子のケースですが、本人のなかでの得手不得手の話で、誰もが、偏差値70の科目をつくれと言いたいわけではありません。本人にとって何かひとつでも好きなものがあること、そして多少なりともそのことで自信を持てるなら、それは必ず勉強を続けるモチベーションになります。それこそが重要なのです。
スポーツも同じです。私は塾の他に、若手のサッカー選手が海外で活躍できるようサポートする仕事もしています。選手たちを見ていると、技術の巧拙よりも、本人がいかにその競技を好きか、自分に自信を持っているか、自己肯定感があるかどうかが、試合中のプレーの優劣に影響すると感じることが多々あります。
また、日本では、例えば野球なら、投打バランスよく訓練することが重視されます(だからこそ、二刀流の大谷翔平選手はあれほどまでに人気があるのだろうと思います)。しかし、人によっては、打撃が得意なら打撃だけ、ピッチングが得意ならピッチングだけを伸ばすほうが、自己肯定感、自信という観点から、選手の総合的な競技能力が高まる場合もあるのではないかと感じています。
話が横道に逸れましたが、この得意を伸ばす教育方法においては、保護者は4科目がバランスよくできていなければならないという幻想を捨てる必要があります。苦手科目はある意味では苦手なままであるという事実を引き受け、得意なものを伸ばしてやることが子どもにとってもいいことなのだと信じて、その気持を持ち続ける覚悟が必要です。
地頭のよさは生まれつきのものだけではありません。保護者が子どもの能力を見出し、信じることによって、後天的に伸ばせるものでもあるです。