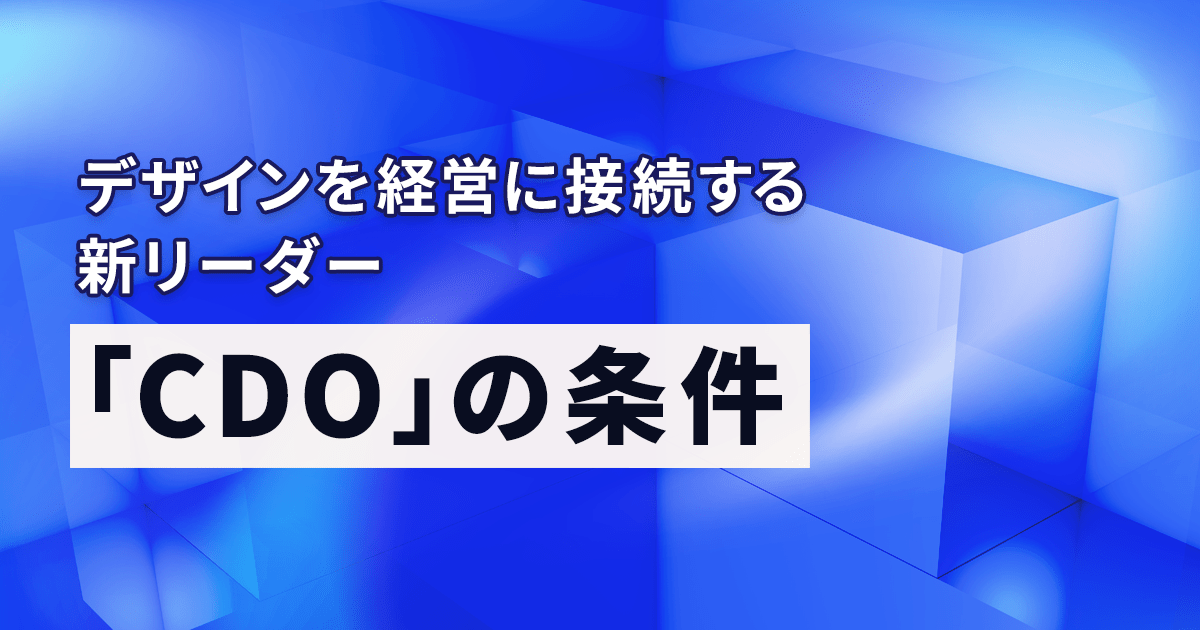
銀行窓口、通帳、ATM――。堅くて保守的なイメージの強いメガバンクから「デザイン」を連想する人は少ないだろう。しかし三井住友銀行(SMBC)では、2016年に発足したデザインチームが、アプリのUI改善からブランドづくり、さらに2030年の未来店舗構想に至るまで、その役割を大きく広げてきた。しかも、その推進役を担ったのはデザイナーではなく、事業部門出身のマネジャー、中村裕信氏だ。経営とデザインをつなぐ“翻訳者”としてのリーダーシップを聞いた。
「銀行不要論」に向き合い、デザインで存在意義を示す
勝沼 銀行の中に“デザインチーム”があると聞くと、少し意外に感じる方も多いと思います。SMBCでは、デザインはどのような位置付けで組織化されているのでしょうか。
中村 組織上は、私が部長を務めていた「リテールIT戦略部」内の1チームとなっています。現在の規模は17人です。
勝沼 デザインチームが事業部門のIT戦略チームにあるというのは、ユニークですね。どういった理由があるのでしょうか。
中村 そもそもデザインに注力するきっかけは、インターネットバンキングをより使いやすく改善することでした。2016年のチーム発足当時はスマートフォンの普及が進み、ネットバンキングが急速にお客さまとの重要な接点になりつつある状況でした。その担当部署がリテールIT戦略部だったため、デザインチームもそこで誕生しました。現在は役割を大きく広げていますが、所属がリテールIT戦略部のままなのは、当時の経緯を引き継ぎつつ、社会におけるデジタルシフトが加速する中、ビジネス面でのデザインの役割、重要性が一段と高まっているからです。
 Photo by YUMIKO ASAKURA
Photo by YUMIKO ASAKURA
勝沼 デザインチーム発足以前にも、デザインが必要になる場面はあったと思います。そのときはどのように対応していたのでしょうか。
中村 当時は、プロジェクトごとに外部のデザイン事務所へ依頼していましたね。ただ、その事例が社内で共有されることはほとんどなく、デザインを全体的に捉える視点も欠けていたんです。SMBCのサービス全体で体験の質を高めるには、やはりインハウスのデザインチームが必要だと考えました。
勝沼 こうした問題意識を現場以外に理解してもらうのは、簡単ではないと感じます。経営層とはスムーズに共有できましたか。
中村 むしろそこは経営層の決断でしたね。おそらく、銀行ビジネスの在り方そのものに強い危機感を抱いていたのだと思います。
そもそも銀行は、人々が「行きたい」と思って訪れる場所ではなく、必要な用事があって初めて足を運ぶ場所です。もし行かずに済むなら、その方が望ましいと考える人が多いでしょう。そこにデジタルの普及が重なり、新興の金融機関や新しい送金手段が次々と登場した結果、「銀行不要論」までささやかれるようになっていました。
銀行の存在意義そのものが問われる状況で、お客さまにどんな価値ある体験を提供し、銀行の役割を示すことができるのか――。その問いに対する答えとして導き出されたのが、「デザインのトータルな活用」だったのです。







