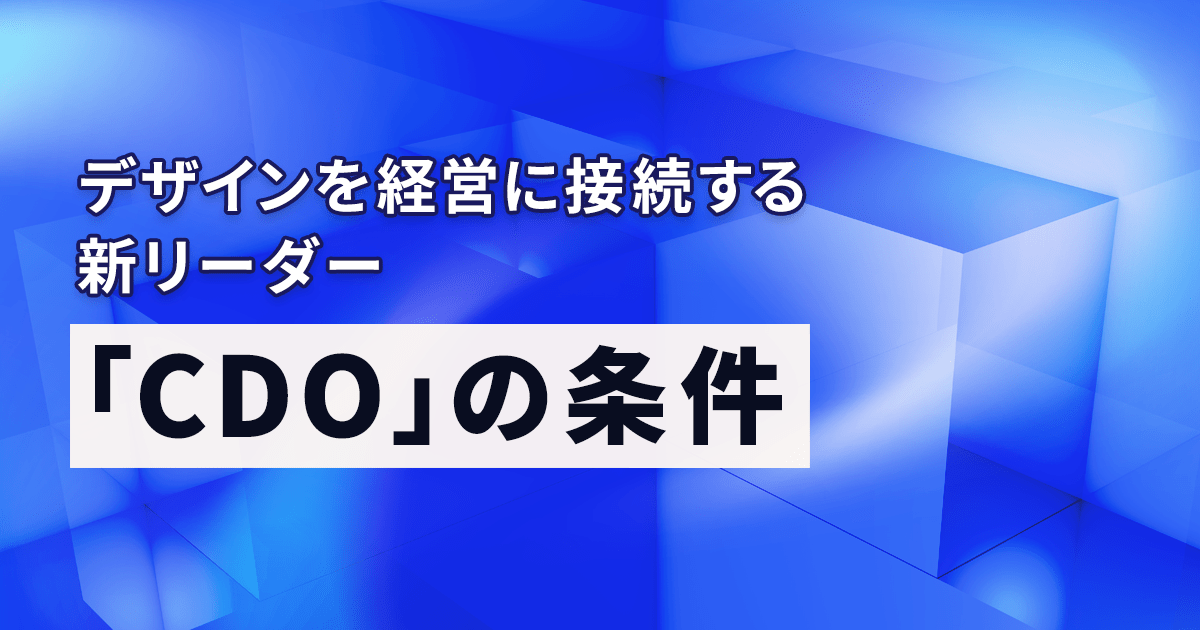
BtoB製品には「性能や価格こそ重視され、デザインは二の次」という思い込みがある。だが、半導体製造装置、産業印刷機や医療機器などのBtoB分野を拡大するキヤノンは、むしろ高いクオリティーのデザインを不可欠な要素と位置付けている。顧客の事業を深く理解したリサーチや、人間工学・認知科学に基づくユーザビリティー設計など、デザインは単なる見た目の調整ではなく、事業の成功を左右する戦略的な役割を担う。こうしたデザインの新たな価値をどう実現しているのか。キヤノン総合デザインセンター所長の石川慶文氏に聞いた。
BtoB事業拡大がけん引するデザイン部門の進化
製品から空間まで広がる役割
勝沼 先ほど、一般には公開されていないというキヤノンのショールームを拝見しましたが、産業印刷機や医療機器といったBtoB製品のスケールやデザインの精緻さにとても驚きました。キヤノンの製品ラインアップは、想像以上に多岐にわたっていますね。
石川 キヤノンはカメラやプリンターのイメージが強いと思いますが、実はそういったコンシューマー製品よりも、半導体製造装置、産業印刷機や医療機器といったBtoB分野のビジネスの割合が高くなっています。
それがデザイン部門の仕事にも大きく影響しています。歴史が長いのはもちろんプロダクトデザインですが、現在の総合デザインセンターには、デザインリサーチ、UX(顧客体験)デザイン、ユーザビリティーデザイン、コミュニケーションデザイン、CG、空間デザイン、デザインプロモーションの計八つのチームがあります。
中でもBtoB事業の拡大に合わせて重要度が増しているのが、デザインリサーチとユーザビリティーデザインです。BtoBビジネスでは、顧客の事業内容はもちろん、設備や施設、ワークフローなど、人の動きまで深く理解することが必須となります。そうした理解を深めるために、デザインリサーチチームは、関連する専門知識を身に付けた上で、現地調査を行い、その内容をレポートにまとめます。一方、ユーザビリティーチームのメンバーは人間工学や認知科学のエキスパートで、デザインリサーチチームに同行し、個々のユーザーの課題を発見し、解決に導く役割を担っています。
勝沼 キヤノンのビジネスモデルが変化するのに伴って、総合デザインセンターの機能も拡張しているんですね。
石川 この10年ほどで総合デザインセンターの機能を着実に広げてきました。近年力を入れているのはCGと空間デザインです。産業印刷機器や医療機器は大型なので、単体のデザインだけでなく、実際に空間にどう設置されるかを具体的に示す必要があります。製品をリアルに表現するCGと、その使用環境を伝える空間デザインは、ショールームや展示会に加え動画のプレゼンテーションが一般化しているBtoBビジネスに欠かせない要素です。
 Photo by YUMIKO ASAKURA
Photo by YUMIKO ASAKURA
勝沼 キヤノンは世界各国で事業を展開しています。デザインチームも各国に分散しているのですか。
石川 デザイン拠点は東京、オランダ、香港の3カ所です。東京のデザインチームは本社に属し、全体のデザイン戦略を立案しています。海外のデザインチームの知見を学び、私たちの意見も伝えながら、製品ラインアップ全体で統一して使用する、造形や色などの「デザイン言語」を共有しているのです。特に欧州のデザイナーのデザインレベルは非常に高いので、それを私たちが吸収することで、製品のクオリティーを上げていくことが大切だと考えています。







