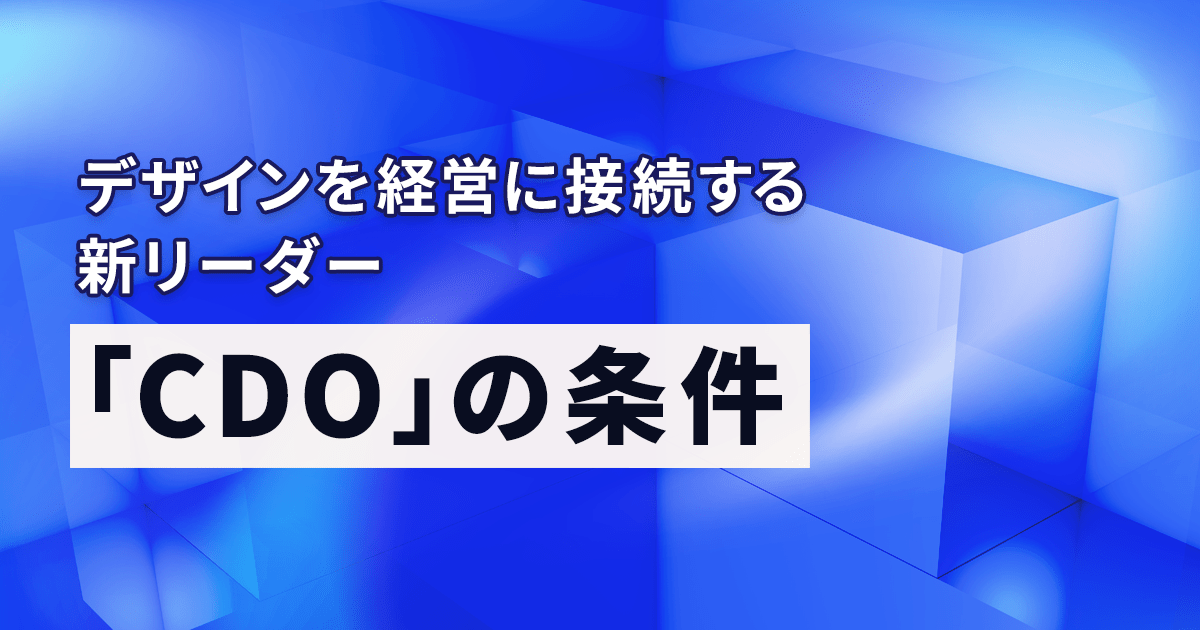
ビジネスとデザインの関係を語る際に、ソニーの取り組みを例に挙げるのは「鉄板」ともいえる。そこで示されるデザインの多くはプロダクトであり、グラフィックだが、近年、それらとは異なる「デザインの力」がソニーのビジネスを動かしている。現在、エンタテイメントに軸足を置くソニーが描いた10年後のありたい姿「Creative Entertainment Vision」。その作業にグループのデザインを統括する組織も大きく関与した。ソニーグループのデザインを統括するクリエイティブセンターの石井大輔氏に話を聞いた。
デザイン組織の形が「デザイン経営宣言」と一致
勝沼 現在のソニーグループのデザイン組織の体制を教えていただけますか。
石井 私が責任者を務めるクリエイティブセンターが、デザインやブランドに関わる活動を統括していますが、そこには、インキュベーションデザインとコーポレートブランディングという二つの部門があります。
インキュベーションデザイン部門の役割は、事業部の製品やサービスの開発を通したイノベーションへの貢献です。新しい製品やサービスのアイデアを提言して、製品化、サービス化することに貢献していくのがこの部門のミッションとなります。
一方のコーポレートブランディング部門は、会社のロゴやブランドをデザインするだけでなく、ソニーグループのトータルなメッセージングやコミュニケーションをサポートします。そうした活動を通して、企業ブランドの価値向上を目指すのがこの部門の役割です。
勝沼 2018年に経済産業省と特許庁が発表した〈「デザイン経営」宣言〉は、「イノベーションに資するデザイン」と「ブランド構築に資するデザイン」をデザイン経営の2本柱と定義しています。現在のソニーグループのデザイン体制は、まさにそれと合致していますね。
石井 結果的にそういう形になっています。ソニーはプロダクトデザインに強いというイメージがあると思いますが、現在は、プロダクト、UI(ユーザーインターフェース)、コミュニケーションといった各デザイン領域の重要性がほぼ等価になっています。
勝沼 ソニーのデザイン部門が、グループ会社のコーポレートコミュニケーションを横断的に手掛けるというのは、以前にはなかったことですよね。
石井 ソニーセミコンダクタソリューションズ(SSS)のコーポレートビジョンの策定プロジェクトは一つの大きな成果かと思います。新しい会社や新規事業を立ち上げる際は、パーパスをはじめとする言葉のデザインや、それを世の中に伝えていくコミュニケーションのデザインが必要になります。SSSのケースでは、どういったビジョンを持つ会社なのかという定義付けから始めて、ブランドムービーやウェブサイトの改修まで手掛けました。
ソニー・ホンダモビリティでは、新しいオフィスを開設する際の空間デザインを手掛けましたし、その他にも、地方に拠点をつくる際の地域社会との関係づくりなどのデザインを求められたこともあります。クリエイティブセンターの役割は、年々拡張しているといえますね。
 Photo by YUMIKO ASAKURA
Photo by YUMIKO ASAKURA







