スマホやゲーム、タブレット、パソコンなどのデバイス・コントロールができないと、生活リズムは整いません。
「夜、子どもが隠れてスマホを見ているため、注意をするのですが、逆ギレされるんです」という相談はとても多いです。
しかし、中学生までは子どもとケンカしてでも、ここはコントロール下に置きたいところです。保護者の覚悟が試される問題とも言えるでしょう。
「約束が守れないようなら、スマホを解約する」くらい強めに言ってもいいでしょう。
保護者が子どものデバイス・コントロールをできないと、家庭内暴力へ発展していくおそれもあります。
まず、「スマホやゲーム、パソコンの使用は○時まで」と、学習と関連付けて保護者と子どもで話し合い、ルールを作りましょう。
そして、その時間以降は、子ども部屋ではなく、居間などの決まった場所にデバイスを置くことを決めます。
このルールでは、子どもだけではなく、家族みんなが同じルールに従うことが大事です。
例えば、午後10時以降は、大人も子どももデバイスを見ることを終え、居間の決まった場所に置くといった具合です。
「夜更かしをする子ども」
に効き目のある4つの習慣
また、夜更かしをする子どもには、以下のような4つの習慣を付けましょう。
(2)寝る1時間前からスマホやタブレットの画面を見ない
(3)毎晩、お風呂に入る
(4)朝、子どものテーマソングを流す
(1)起床時に朝陽を浴びると、体内時計がリセットされます。
睡眠に関わるホルモン(セロトニン)の分泌が促され、夜のスムーズな睡眠がもたらされます。
カーテンを開け、朝陽を浴びるだけでも構いません。可能ならば、朝起きたら子どもと一緒に外に出て、50メートルくらい歩くとさらにいいでしょう。
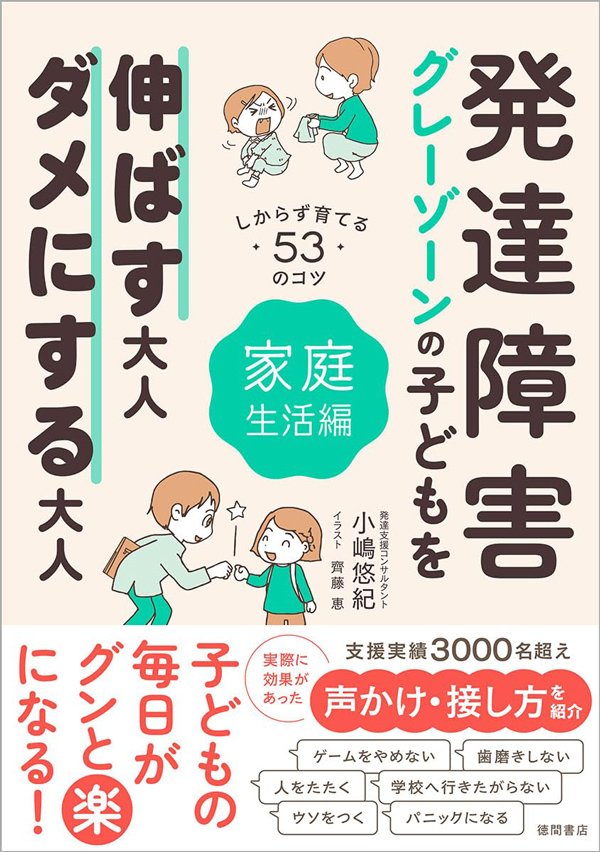 『発達障害・グレーゾーンの子どもを伸ばす大人、ダメにする大人 家庭生活編』(小嶋悠紀 徳間書店)
『発達障害・グレーゾーンの子どもを伸ばす大人、ダメにする大人 家庭生活編』(小嶋悠紀 徳間書店)
(2)スマホやゲーム、パソコンの画面からは、ブルーライトと呼ばれる強い光が放たれています。
寝る直前までこのブルーライトを浴びていると、脳が覚醒し、寝付きにくくなります。
(3)入浴は、安眠をもたらす効果があるとされています。
入浴によって上昇した深部体温が下がっていくときに、自然な眠気がもたらされるからです。
(4)子どもの好きな曲を、朝のテーマソングにして流しましょう。
「この曲が終わる前に顔を洗おう」など、テーマソングを活用して、子どもの次の行動を促します。
元気な曲調に後押しされ、朝の準備がスムーズにできる子も多いです。
 同書より転載
同書より転載







