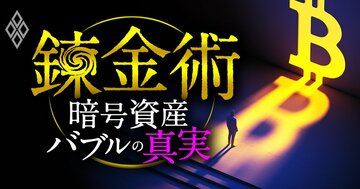例えば、自身の不注意で洗濯機のホースが外れ、自室の床が水浸しになった場合を考えてみてほしい。階下への賠償は個人賠償責任保険でカバーできるかもしれないが、自室の床や壁紙の張り替え費用は水ぬれを補償する特約に加入していなければ、すべて自己負担となる。その損害額は数十万円、場合によっては百万円を超えることもあり、目先の保険料を抑えたことで、かえって大きな出費を強いられることになりかねない。
まずは一度、ご自身の保険証券を手に取り、どこまでカバーされているのかを改めて確認することが重要だ。これは単なる保険料の値上げという側面だけでなく、自身の生活に潜むリスクを再点検し、本当に必要な補償を見極める絶好の機会と捉えるべきだろう。
意外と知られていない
「共用部保険」の実態
先に挙げた個人の火災保険であれば、更新のたびに保険料と向き合い、見直しを検討するだろう。だが、管理組合で加入するマンション総合保険(共用部保険)についてはどうだろうか。保険料は“管理費”という大きな財布から支払われ、自分事として捉える機会はほとんどない。理事会や管理会社が「例年通り」で更新を続けていても、多くの住民はその契約内容はおろか、保険料の総額すら知らない、といったケースも少なくないのだ。その結果として見過ごされがちなのが、主に以下の4つのポイントである。
1.「再調達価額100%」という思い込み
多くのマンション総合保険では、保険金額の基準となる付保割合を再調達価額(同等の建物を再建するのに必要な金額)の100%に設定されていることが珍しくない。これは、マンション1棟が全焼し、建て直す事態を想定したものだ。
しかし、現在のマンションは建築基準法により防火区画の基準が設けられており、一部屋から出火しても隣室への延焼リスクは極めて低く抑えられている。実際に火災が発生しても、被害は上下左右の部屋に及ばず、鎮火後に普通に生活しているケースがほとんどである。全焼リスクが限りなくゼロに近いにもかかわらず、100%の補償をかけ続けるのは、明らかに過剰と言えよう。意識の高い管理組合では、これを50~60%、中には30%程度まで見直している事例もある。