おそらく、彼女自身が入社した当時、上司からそのような指導を受けていたのでしょう。彼女が入社したのは平成でしたが、昭和の体質が残る上司が多くいた時代です。
本来、有給休暇はどんな目的であっても自由に取得できるもので、会社にその理由を報告する義務はありません。ただし、会社側には「時季変更権」があり、繁忙期などにどうしても休むことが難しい場合、別の時期に休んでほしいと依頼する権利が認められています。
K子さんもその点は理解しており、夏休みはお盆の時期を避けて取得し、今回の秋休みも2日は繁忙期にかかるものの、その他の日程は一般的に忙しくない時期を選んで休暇を申請したそうです。
有休取得は正当な権利なのに
世代間の価値観に大きなズレ
有休でいえば、もう1つ友達の会社にはうらやましいことがあって、とK子さんは言います。
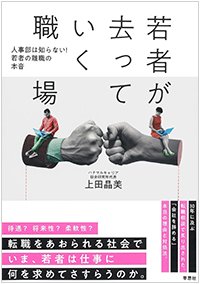 『若者が去っていく職場――人事部は知らない!若者の離職の本音』(上田晶美、草思社)
『若者が去っていく職場――人事部は知らない!若者の離職の本音』(上田晶美、草思社)
「1時間単位で有休が取れるの、よくないですか?だって会社終わりにライブがあるときなんか、1時間早く上がれれば行けるのに、ということがよくあって。終業が18時であっても、その日だけ17時に終われれば、18時には会場に着いて間に合うということがありますよね。それを導入してほしい、と今度人事の人に言ってみるつもりです。そうしたら、他の日は少しの残業くらいかまわないし、もっともっと時間中はお客さんに声かけて、頑張りますよ」
このケースは、まさに「働き方改革」と現場の意識のギャップが浮き彫りになった例です。企業側は有給休暇の取得を促進する方向に進んでいるものの、実際には昭和的な価値観が根強く残っている職場も少なくありません。特に管理職であるミドル世代の中には、「有給休暇を積極的に取る=仕事の責任感が足りない」と感じる人もまだ多くいるため、K子さんのように正当な権利を行使しただけなのに、反感を買ってしまうケースもあるのです。
本来、有給休暇とは、労働者がリフレッシュし、仕事のパフォーマンスを向上させるための大切な権利。有休を取ることによる個人の充実感が、最終的には仕事の生産性向上にもつながるという考え方が、もっと広まるべきでしょう。







