これはクスリを飲んだという安心感が自然治癒力を引き出すためとの説もありますが、思い込みがいかに身体に影響するかという一例といえるでしょう。
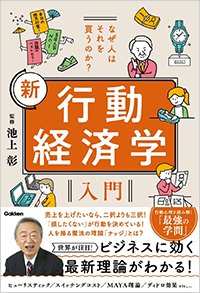 『なぜ人はそれを買うのか?新 行動経済学入門』(池上 彰、Gakken)
『なぜ人はそれを買うのか?新 行動経済学入門』(池上 彰、Gakken)
そのほか、実際は安いお酒であっても「これはめったに手に入らない高級酒ですよ」と言われて、そう思い込んで飲むとおいしく感じたり、「この木はうるしだ」と伝えると、本当はうるしの木でなかったとしても皮膚がかぶれてしまったりすることがあるといいます。
つまり、人は知識によって知覚が影響を受けるということです。
このようなプラシーボ効果を使って悪事を働く例がある一方で、この心理作用はプラスにも活用できます。
たとえば、上司が部下に「キミはやれば必ずできる」と繰り返し語りかけて、そうだ、自分はできるんだと思い込ませるという手法です。
プラシーボ効果をどう活かすかは、心がけ次第というわけです。







