人付き合いがあまり得意でなくても、それが大きな問題になることは少なく、自分らしいスタイルで乗り切りやすいという側面があります。
ところが、社会人になると状況は大きく変わります。仕事には必ずしも「正解」があるわけではなく、どう進めるかを自分で考えて判断しなければならない場面が多くなります。
また、複数の業務を並行して進める必要があったり、相手の立場や感情に配慮したコミュニケーションが求められたりと、柔軟さや調整力が重要になります。
学生時代は特に困りごとがなかった方でも、社会に出てからこうした違いに戸惑い、「なぜかうまくいかない」と感じることが出てくるのです。
発達特性が強みになる
仕事はあるはず
さらに、会社によっても環境はさまざまです。
ルールや手順が明文化されていて、役割がはっきりしている職場では力を発揮できた人が、マニュアルにできない対応や察することが求められる職場では、不安や困難を感じ自信をなくしてしまうこともあります。
また、実務をコツコツこなすことが得意だった人が、管理職になって人の調整やマネジメントが求められたとたんに難しさを感じることもあります。
一方で、その特性が職場で大いに活かされるケースもあります。
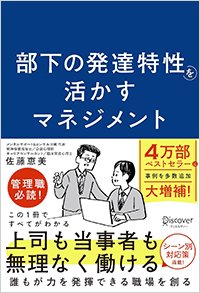 『部下の発達特性を活かすマネジメント』(佐藤恵美、ディスカヴァー・トゥエンティワン)
『部下の発達特性を活かすマネジメント』(佐藤恵美、ディスカヴァー・トゥエンティワン)
たとえば、細かい部分に気づく力がとても優れていて、全体をざっくりと把握するのはやや苦手な方がいたとします。スピード重視の業務では「遅い」と言われてしまったかもしれませんが、法務や品質チェック、校正などの「細部の正確さが重要な仕事」では、その能力が高く評価され、「あの人がいれば安心」と頼りにされているケースがあります。
また別の例では、「興味のある分野に対してとことん集中できる」特性を持つ方が、IT企業でプログラムの不具合(バグ)を徹底的に探し出す仕事に就き、誰も気づかなかった問題を発見して「職人技」と称賛されたということもありました。
これは、その人自身や職場がその特性を理解し、環境との相性を見つけた結果と言えます。
このように、特性がどう現れるかは、本人の努力だけでなく、「どんな環境にいるか」が大きく関係しています。だからこそ、「自分に合う場所ややり方」を見つけることがとても大切なのです。







