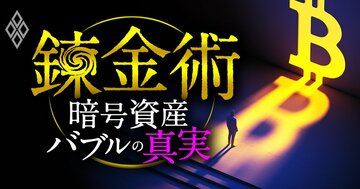給与収入160万円の人がiDeCoで月1万5000円を積み立てた場合の節税効果を見てみよう(税務上の扶養家族はなし)。
昨年までの節税効果:2万7200円(所得税9200円、住民税1万8000円)
今年からの節税効果:1万8000円(所得税ゼロ、住民税1万8000円)
所得税の減税効果はゼロになったが、住民税は1万8000円の節税効果は残る。どういうことか。
国民民主党が掲げた「年収の壁問題」に端を発した基礎控除拡大の減税措置は、「所得税だけ」なのだ。住民税の基礎控除については、地方自治体首長の反対により減税は行われていない。
iDeCoを続ける意味はある。節税効果はiDeCoのメリットの一つにすぎず、節税効果がない人がやってはいけないというルールはない。
例えば第3号被保険者(会社員、公務員の社会保険上扶養されている配偶者)は、収入がなくてもiDeCoの加入資格はある。
節税効果は少なくても、将来に向けて積み立てを続けることが大事なので、ぜひ継続を。
◆ケース4
→今年の公務員向けライフプランセミナーでこの質問が多かった。得する掛金はわからないと答えている。
公務員は、定年時に退職一時金が支給される。勤続年数が38年間の場合、退職所得控除額は2060万円。退職金の金額は自治体や職種、役職在籍年数により異なるが、2000万円前後が多い。
これまでは公務員のiDeCo掛金は少なかったので、受取り時の課税については心配する人は少なかった。ところが27年から5万4000円に拡大するため、にわかに受取り時の税金を心配する人が出てきたのだ。
掛金を増やすより、退職所得控除額の範囲内になるように少ない掛金で積み立てした方が、税金がかからずトクではないか……と質問を受ける。企業年金のない公務員は、以前からiDeCo好きが多い。
ただ、税金がかからないように掛金を設定したとしても、投資信託の運用がうまくいって思いのほか積立金が増える可能性がある。そうすると、課税の部分が出てくる。
受取り時の積立金は未来のことでわからないので、トクする掛金はわからないと答えるしかないのだ。
掛金を増やすと毎年の節税効果は大きくなるが、受取り時の課税対象は増える。掛金を少額にしておくと節税効果は少ないが、受取り時の税金は少なく抑えられる可能性はある(運用で増えたらその限りではない)。
「公務員は掛金〇万円がベスト」といった答えは出せないので、「今」と「将来」の節税効果のバランスを取りながら自分で決めるのがいいと思う。