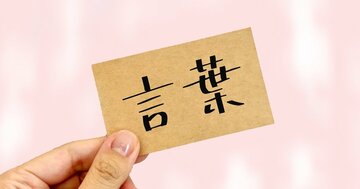漢字も増やして、試してみましょう。
「でたらめ記者」。はて、誰のことか。大正時代に首相を務めた原敬が、大阪の新聞社で社長をしていたころに、連載随筆のペンネームとして使っていた。
随筆は、外国との付き合いに不慣れだった日本人に、習慣の違いや交際の仕方についてユーモアを交えて説き評判になった。後に平民宰相(首相)と呼ばれた人となりがわかる。
原は多くの文章を残した。中でも「原敬日記」には、古い勢力と闘い政党内閣を作る道のりが語られている。大正デモクラシーの基礎資料だ。
1921年11月4日、原は若い男に刺されて亡くなり、自宅から遺書が見つかった。栄典は不要で、葬儀や墓は簡素に、などと書かれていた。遺言通り岩手県盛岡市にある墓には肩書もなく「原敬墓」と彫られている。事あるごとに先人の墓参りをする政治家は多いもの。ぜひこの墓に学んでほしいものだ。
随筆は、外国との付き合いに不慣れだった日本人に、習慣の違いや交際の仕方についてユーモアを交えて説き評判になった。後に平民宰相(首相)と呼ばれた人となりがわかる。
原は多くの文章を残した。中でも「原敬日記」には、古い勢力と闘い政党内閣を作る道のりが語られている。大正デモクラシーの基礎資料だ。
1921年11月4日、原は若い男に刺されて亡くなり、自宅から遺書が見つかった。栄典は不要で、葬儀や墓は簡素に、などと書かれていた。遺言通り岩手県盛岡市にある墓には肩書もなく「原敬墓」と彫られている。事あるごとに先人の墓参りをする政治家は多いもの。ぜひこの墓に学んでほしいものだ。
20字減って、354文字です。大人が読んでもおかしくないと自分では思っています。
小論文や企画書でも
まずは200字から始めて
私は朝日カルチャーセンターで、「短文力を鍛える文章教室」を持っています。受講生には600字の作品を提出してもらっています。なぜ600字なのでしょうか。
朝日新聞の「天声人語」、読売新聞の「編集手帳」、毎日新聞の「余録」、日本経済新聞の「春秋」、産経新聞の「産経抄」など、大手新聞の一面コラムがほぼ500字弱から、600字余りでできているからです。
かつてはどのコラムもいまより長かったでしょう。新聞の活字が大きくなるにつれて、コラムの文字数は減ってきました。いまはそれぐらいの文字数で、1つの作品ができています。
このぐらいの分量があれば、文章に工夫を凝らして、1つのことが言えるということです。
大学入試の小論文は800字ぐらいで書かせるものが多いようです。2023年度の問題を見てみましょう。
北海道大学文学部人文科学科(後期)
人の存在をアルゴリズムとデータの流れとして受け入れるのかと論じた文より、具体例を挙げて考えを書く。(750字)
人の存在をアルゴリズムとデータの流れとして受け入れるのかと論じた文より、具体例を挙げて考えを書く。(750字)
お茶の水女子大学文教育学部人文科学科(後期)
戦争と平和を論じた3つの英文を読んで要約し、自身でテーマを決めて人文的な関心に沿って考えを述べる。(800字)
戦争と平和を論じた3つの英文を読んで要約し、自身でテーマを決めて人文的な関心に沿って考えを述べる。(800字)