人間の側の認識不足も
被害が拡大した一因
それを検証したのが、岐阜大学応用生物科学部附属野生動物管理学研究センターの「乗鞍クマ人身事故調査プロジェクトチーム」である。同チームは、事故の目撃者らから独自に聞き取り調査を行ない、「乗鞍岳で発生したツキノワグマによる人身事故の調査報告書」(2010年3月)として公表した。
〈通常クマが何のきっかけもなく走り出し人前にでるということは考えにくく、周囲に隠れる場所のない乗鞍のような高山帯においてその原因となる可能性が高いのは人間との遠・近距離での接触である。おそらく、斜面上部で人とのなんらかの接触があったのではないだろうか。
ひとつの可能性として、本個体が採食に夢中になっているところで突然人に大声を出されるなどしたため、驚き斜面を駆け下りたところ車の往来する道路に出てしまいパニックになり、たまたま接触したバスを攻撃したということが考えらえる。
本個体がパニック状態であることは、その後の駐車場の柵や石壁での行動から明らかである。通常森林内であれば人間との遭遇により驚き逃げたクマは人の目の届かない藪や林内に入り落ち着きを取り戻すことができるが、今回は高山帯のためそのような環境がなかったと考えられる〉
いくつかの偶発的な不幸が重なってクマが追い詰められ、この事故が起きたことは間違いなさそうだが、人間の側に「乗鞍岳周辺はクマの行動圏である」という認識が低かったことも、被害が拡大した一因であることは否定できない。
この事故から得た教訓は
「決してクマに向かっていくものではない」
事故を振り返って小笠原が思うのは、もしあのとき石井が襲われておらず、クマだけが単独でいたら、ということだ。
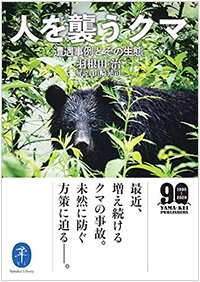 羽根田治『人を襲うクマ』(山と溪谷社)
羽根田治『人を襲うクマ』(山と溪谷社)
「手を叩いたり大声を出したりするのは、クマを威嚇することになるので、やはり危険だと思います。しかもあのときは周囲を取り囲んでいた人たちから『わーっ』『きゃー』という悲鳴が上がっていたので、よけいにクマも興奮したのでしょう。でも、もしあのままにしていたら、石井さんは命を落としていたかもしれません。放っておくわけにはいきませんでした」
ただ、被害者が出ておらず、ふつうの状態でクマがいたときには、自ら静かに遠ざかること。観光客や登山者がいる場合は、静かに避難させるだけにとどめること。決してクマに向かっていくものではない。それがこの事故から得た教訓だと、小笠原は言う。







