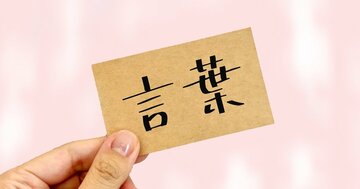熟練者にとっては当たり前のゴールでも、新米の人にとってはそうであるとは限りません。「ゴールは何か」「何のためにそうするのか」がわからないと、1つ1つの手順を教わっても、細かい判断を間違えることがあります。
何かを主張したり論じたりするときも、先に主張や結論を言って、その後で根拠や理由を言う方がわかってもらいやすくなります。
私は昔、「最後まで読まないと結論がわからない方が、意外性があって面白いんじゃないか」と思っていましたが、「意外な結末」が歓迎されるのは推理小説など、「そこまでの筋道」を楽しむジャンルに限られたことです。
論文やレポートでは早めに結論がわからないと、読む人にストレスをかけてしまいます。
聞き手の疑問を想定すれば
説明は格段にわかりやすくなる
聞き手とのやりとりが可能な場で説明をするときは、「自分が話すだけで終わりにしない」ことも重要です。
相手が目の前にいると、相手が何をどれだけ知っているか、相手の興味はどこにあるか、相手がこちらの話をどれほど理解できているかということが、相手の様子からわかることもありますし、相手から直接質問を受ければ、相手のニーズにあった説明ができる可能性が広がります。
何より、「人はこういうことを知りたいのだな」「こういうことがわかりづらいんだな」という情報を得ることが、自分の学びになります。
第三者から見ても、話し手と聞き手のやりとりのある説明は、話し手が一方的に話すよりもわかりやすいものです。解説書などで、先生と生徒の対話形式がよく採用される理由もそこにあります。
生徒役がときどき言葉を発することによって、説明を聞いている人たちが引っかかりがちなポイントで立ち止まり、補足の説明をすることが可能になるのです。
たとえ一方通行の説明しかできない場合でも、聞き手がここでこういう疑問を持つのではないかと予想しておけば、それに答えるための準備ができます。そのためには、自分の頭の中に「ものわかりの悪いツッコミ役」を住まわせておくことが重要です。