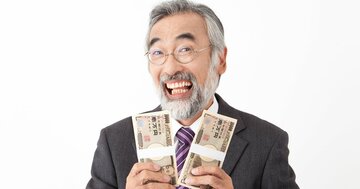そして、あまりにも有名な「少年よ、大志を抱け」の言葉を残したウィリアム・S・クラーク博士。彼が教頭を務めた札幌農学校(現在の北海道大学)の使命は、北海道開拓という国家プロジェクトを担うリーダーの育成そのものでした。
教科書の外から、時代を変えた実務家たち
彼らに共通するのは、教科書の外にある「リアルな知見」と「新しい視点」を持ち込み、旧態依然とした空気を一変させたことです。彼らの存在そのものが学生の心を揺さぶり、社会をリードする新しい時代の雰囲気を作り上げていったのです。当時の彼らは、まさに明治の時代に「サードキャリア」を実践した先駆者でした。
ここでいうサードキャリアとは、組織のなかで働く第一のキャリア、自立を求める第二のキャリアを経て、社会とともに新しい価値を生み出す第三のキャリア(=共創と貢献の生き方)を指します。
自身の経験を再構築し、異なる社会のなかで新しい価値を生み出した彼らの挑戦が、後に日本の近代化を支える原動力となりました。
そして2025年の今、歴史は繰り返しています。
社会が複雑化し、未来が誰にも予測できなくなったこの時代に、再び「実学」の価値、つまりビジネスの最前線で培われたあなたの経験に、白羽の矢が立っているのです。
その最も象徴的な舞台が、いま劇的な変化の渦中にある「大学」です。
社会、企業、大学…リアルな“実務教育”を求めて回り始めた
「大学教授」と聞くと、一つの専門分野を何十年も研究し続ける研究者の姿を思い浮かべるかもしれません。しかし、そのイメージはもはや過去のものとなりつつあります。
人生100年時代を迎え、大学は「18歳の若者が4年間だけ学ぶ場」から、社会人がキャリアを再構築するための「学び直しの拠点」へと、その役割を大きく変えようとしています。
かつて「象牙の塔」と揶揄された大学は今、文部科学省の強力な後押しもあり、地域社会や企業と連携し、新たな価値を創造する地域のハブとして「社会変革のエンジン」となることを求められているのです。