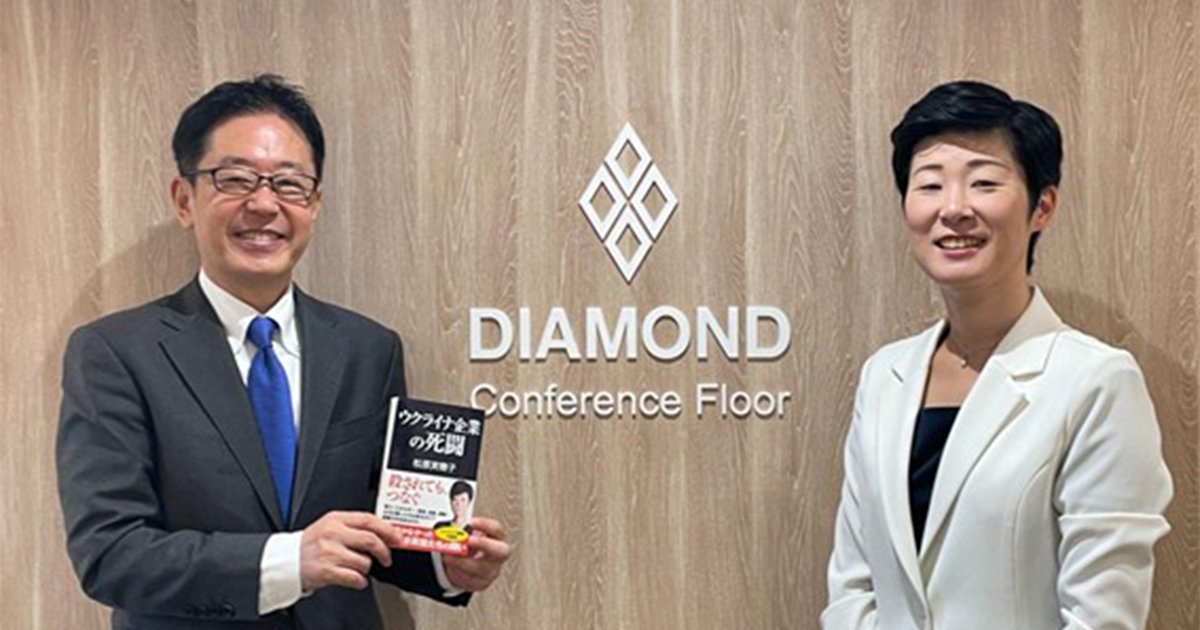 Photo:Diamond
Photo:Diamond
人気連載『組織の病気』の著者、秋山進氏が防衛省出身でサイバーセキュリティの専門家であり、『ウクライナ企業の死闘』の著者でもある、NTTチーフ・サイバーセキュリティ・ストラテジストの松原実穂子氏と対談。前後編の前編では、ウクライナはロシアからのサイバー攻撃をどう防いだか、戦時に狙われるインフラ企業の実態、日本の安全保障の問題点から、台湾有事に際してどのような教訓を学べるかを語り合った。
戦争中も普通の人たちが企業人として仕事ができているという驚き
秋山進氏(以下、秋山) 松原さんの新著『ウクライナ企業の死闘』(産経新聞出版)を拝読しました。ロシアによる侵攻下で、電力・エネルギー、通信、金融、運輸といった重要インフラを守るため、企業人たちが命をかけて戦い続ける姿を描かれています。戦闘についてはよく見聞きしますが、戦時下のインフラ企業従業員という、これまでにない視点で本を書かれていますね。
松原実穂子氏(以下、松原) 戦争開始から約半年が経過した2022年10月以降、ロシアはウクライナの電力とエネルギーインフラを繰り返し攻撃しました。極寒の時期に停電を多発させて、ウクライナ人の心を折り、継戦意思をくじく狙いがありました。
それでも尚、ロシアの軍事侵攻当初、2週間も持たないと言われていたにもかかわらず、ウクライナは、3年半以上闘い続けています。その底力はどこにあるのかと疑問が浮かびました。
戦争は総力戦です。安全保障の4つの柱はDIMEと呼ばれています。外交(Diplomacy)、インテリジェンス、軍事(Military)、経済(Economy)です。経済、つまり企業活動なくして安全保障は成立しません。軍と政府だけでは安全保障は守れないのです。
ウクライナでは、今でも前線近くであっても、電力やエネルギー、通信、金融、運輸といった重要インフラ企業のごく普通の社員たちがサービスの提供を続け、命を賭して破壊されたインフラを修理・復旧し、地元住民の生活と命を支えています。この視点でウクライナの戦争は一切語られてきませんでした。
しかし、経済があって初めて国民は生活し、生きられる。戦争・紛争下であっても如何に業務継続するかという視点は今まで日本人から抜けていたと思います。ウクライナが全面侵攻を受けながらも主権国家の地位を維持できてきたのは、軍人だけでなく、武器を取らないごく普通の企業人たちが、職務を全うし続けているからです。
秋山 インフラが攻撃対象になるのは、軍の活動と市民生活両方にダメージを与え、相手の戦争維持能力を奪い、国家として機能させなくするということですね。本の中で、ロシア軍がウクライナ南部ヘルソン州の通信事業者たちの事業所を訪れては、担当者の頭に銃口を頭に突きつけ、ネットワークの管理権をロシア側に引き渡すよう命じたという記述がありました。まさに命がけの状況ですね。
松原 ウクライナ最大の電力会社「DTEK」の社長は、海外メディアのインタビューで、軍事侵攻後、毎朝最初の仕事が前日に殺傷された社員の確認になったと語っています。
重要インフラ企業の社長や社員たちの境遇を思って胸が詰まり、執筆するのがつらい時もありました。前線近くでも荷物や人々を運び、破壊された発電所や通信インフラの修理・復旧をしている社員たちは、身の危険にさらされています。停電が多発しているため、デジタル化が進んでいる金融サービスでも現金のニーズが高まりました。攻撃される危険の中、誰かが現金を運び続けているのです。
秋山 ウクライナは2014年のクリミア侵攻後、ある程度備えをしていたため、戦争を持ちこたえているということですが、どのような準備をしていたのですか。







